昨日、夫の母方の祖母の法事に参加してきました。
夫は長男なので義両親に何かと「自分事としてよく見ておけ」と言われていますが、どこか他人事(笑)いつかは義実家の供養に主催者側として関わるときが来るはずなので、嫁としてしっかりしなきゃと思っています。
でも身内の法事って、「どのタイミングで」「誰が呼ばれるのか」「自分がどこまで動くべきか」がわかりづらいもの。
今回は、法事の種類や流れを整理しつつ、「主催者側の嫁」としての立ち位置をまとめてみました。
法事の種類と時期
仏教の法要は、命日からの経過によって区切られています。
| 名称 | 時期 | 内容の目安 |
|---|---|---|
| 初七日 | 亡くなって7日目 | 葬儀の中で一緒に行うことが多い |
| 四十九日 | 亡くなって49日目 | 忌明け。納骨を行う大切な節目 |
| 百か日 | 亡くなって100日目 | しめくくりとして行う家庭も |
| 一周忌 | 亡くなって1年後 | 最初の年忌法要。親族を呼ぶことが多い |
| 三回忌 | 亡くなって2年後 | 一周忌の翌年。ここまでが「大きな法事」 |
| 七回忌 | 亡くなって6年後 | 家族中心で行うケースが増える |
| 十三回忌・十七回忌以降 | 12年、16年後など | 家族のみ、または略式で行うことが多い |
親戚を呼ぶ行事・家族で行う行事
ではどういった規模感で行うものなのでしょう。
| 法事 | 親戚を呼ぶか | 内容の傾向 |
|---|---|---|
| 四十九日 | ◎ 親族を招く | 納骨+食事会を行うことが多い |
| 一周忌・三回忌 | ○ 親族・ごく近しい友人 | お寺での読経+会食 |
| 七回忌以降 | △ 家族中心 | 自宅またはお寺で簡略に |
| 十三回忌以降 | △家族中心〜×行わない | 供花・お供えのみのケースも多い |
ポイントは「三回忌までは親族を呼ぶ」「それ以降は家族中心」が多いという流れです。
地域によって多少の違いはありますが、全国的にこの傾向が主流のようです。
長男夫婦の立ち位置と関わり方
「長男の家が主催側になる」という習わしは今も多く残っていますが、「嫁の仕事」ではなく「家を代表する立場の分担」として考えるのが現代的です。
主催側(施主側)としての主な役割
- 法要の日程をお寺と調整する
- 親族へ案内状を出す
- 当日の受付・お布施・会食の段取り
- 会食の手配やお供え物の準備
ただし、これを一人で抱え込む必要はありません。お寺や仕出し屋さん、親族に相談すれば、かなりサポートしてもらえます。
「分担して無理なく」が今の時代のスタンダードです。
とはいえ地域でギャップがあるかも…
わたしの嫁ぎ先は、夫婦や家族で協力して行事をすすめるのがスタンダードな様子。食事席で同じ卓について食事をとる風景が新鮮でした。
一方で、故郷ではいまだに男尊女卑的な風景が普通に見られます。女性がセカセカと準備をし、座敷に座る暇もなく台所で食事を済ます。お酒が無くなれば女性が気配り。出入口に近い席の端に窮屈に座って世話係…。
家庭差はもちろん、出身地が異なると、風習の違いが必ずあります。嫁に行く女性はギャップに驚いたり、悩んだりするでしょう。
はじめはそのご家庭に習い、先代の風習を受け入れることが必要かもしれません。時間をかけて、時代に合わせた「うち流」を築いていけるといいですね。
まとめ
法事は「家の伝統」や「地域の慣習」が濃く出る行事です。両親や親戚に相談しながら“うち流”を掴むのがいちばんです。
また法事は「形式」ではなく、「想いを伝える場」。昔ながらの形をそのまま続けるよりも、家族が“納得できる形で故人を想う”ことが大切です。
長男の嫁という立場は責任もありますが、「家を大切に思う気持ち」さえあれば、それがいちばんの供養かもしれません。

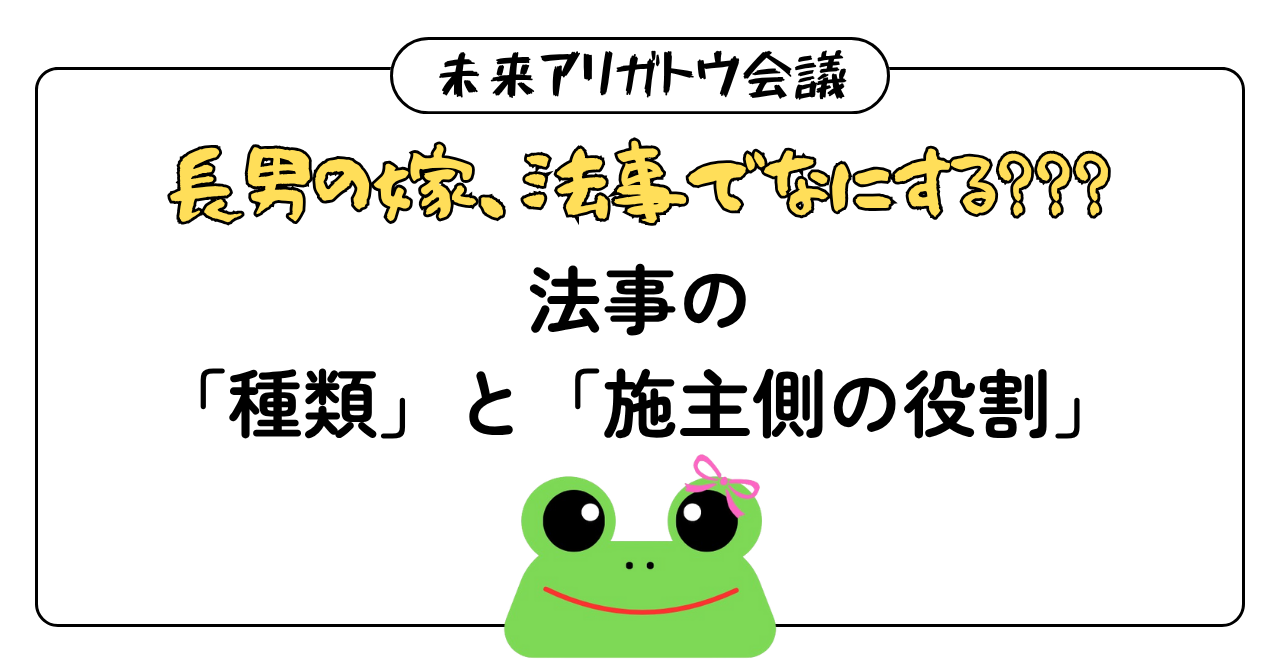
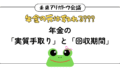
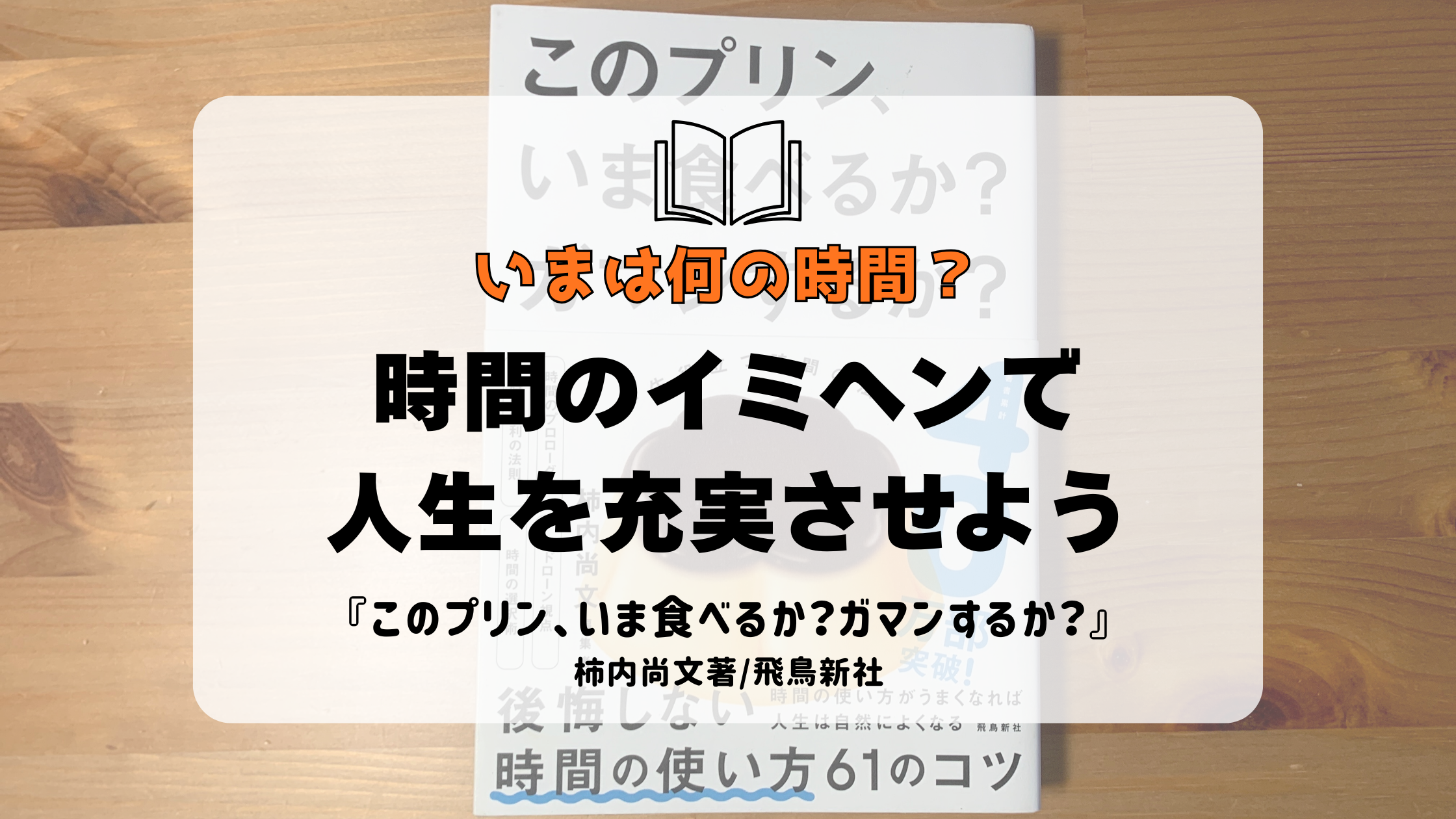
コメント