うちの親は国民健康保険で、ほとんど貯蓄もない。そんなとき「介護が必要になったら、どうやってお金を出していくの?」って不安になりますよね。
実は、介護サービスにはいくつもの公的な補助制度があります。今日は、「子が支える立場」として知っておきたい制度と申請の流れを整理してみました。
基本は“介護保険制度”
65歳以上の人(または40歳以上で特定疾病のある人)は、国民健康保険でも介護保険の対象者になります。最初に「要介護認定」を受けて、必要なサービスを選びます。
費用は1~3割負担
利用者の所得によって負担割合が変わります。
- 年金などの所得が低い人 → 1割
- 所得が中~高の人 → 2~3割
サービス利用時はケアマネージャーさんがプランを立ててくれるので、金額も事前に確認できます。
申請先:親御さんの住む市区町村の介護保険課や地域包括支援センター
持ち物:介護保険被保険者証、印鑑、本人確認書類など
高額介護サービス費制度で、負担が重くなった月をカバー
介護サービスを使っていると、自己負担が思ったより高くつくことも。そんなときに使えるのが「高額介護サービス費制度」。
1か月の自己負担額が上限を超えた場合、超えた分が戻ってきます。たとえば年収が770万円未満の世帯なら、上限は月44,400円ほど。
申請すれば、翌月~数か月後に払い戻しされます。
申請先:親御さんの住む市区町村の介護保険担当窓口
持ち物:高額介護(介護予防)サービス費支給申請書、本人名義の通帳またはキャッシュカード、介護サービス利用明細書、領収書、介護保険被保険者証、印鑑(認印でOK、マイナンバーカードまたは本人確認書類 など
上限額一覧(1か月あたり)
下記は2024〜2025年あたりの改正後データを元に整理しています。
「年収」と記載されている部分はおおよその目安で、「課税所得」や「課税年金収入+その他所得」などで判定される場合があります。
| 区分 | 対象となる世帯(年収目安) | 自己負担上限(月額) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護・市町村民税非課税で老齢福祉年金受給 | 15,000円 |
| 第2段階 | 市町村民税非課税世帯で、年金+その他の合計所得が年80万円以下 | 15,000円 |
| 第3段階① | 市町村民税非課税世帯で、合計所得金額が80万円超~一般並み未満 | 24,600円 |
| 第3段階②(一般所得者) | 年収目安 約81万円以上~約383万円未満 の人(市町村民税課税あり) | 44,400円 |
| 第4段階(現役並み所得者Ⅰ) | 年収約383万円以上~約770万円未満(所得税課税あり) | 93,000円 |
| 第5段階(現役並み所得者Ⅱ) | 年収約770万円以上 | 140,100円 |
補足・注意ポイント
- 判定対象は 65歳以上で介護保険を利用している人がいる世帯全体の所得。サービスを利用していない同居者の所得が影響することがあります。
- 年金収入や給与所得を合算して、課税・非課税の区分で判定されます。
- 毎年8月に「負担限度額認定証」が更新されるため、所得が変わると区分も変わります。お住まいの市区町村の最新案内を必ず確認してください。
- 対象となる「利用者負担」には、介護保険サービスの利用料(原則1割など)のみが含まれ、食費・居住費・日常生活費・住宅改修費などは含まれません。
- 上限額を超えた分が「払い戻される」仕組みなので、まずは支払いが発生したら申請書類を準備することが大事です。
自治体独自の助成も確認
親御さんが低所得なら、自治体ごとにある助成制度もチェック。
例としては――
- 自己負担助成制度:介護施設・グループホームの居住費や食費を補助
- 家族介護慰労金:在宅介護を続けている家族に年10万円前後を支給
自治体によって名前や内容が異なるので、「〇〇市 介護 助成金」で検索すると早いです。
家族ができるサポートの流れ
| ステップ | あなたができること |
|---|---|
| ① 相談 | 市区町村や地域包括支援センターに「介護保険を使いたい」と相談 |
| ② 要介護申請 | 書類記入や訪問調査に付き添ってあげる |
| ③ ケアプラン作成 | ケアマネージャーと一緒に希望を整理 |
| ④ サービス開始 | 負担割合や助成制度を確認 |
| ⑤ 補助申請 | 「高額介護サービス費」や自治体助成を申請 |
| ⑥ 継続フォロー | 介護内容や請求書を定期的にチェック |
こうして見ると、子どもが“お金を出す”よりも、“制度を探す”ことが支えになるんですよね。
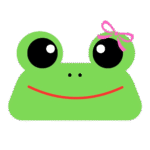
こうしてみると、親の住む自治体で申請を必要とすることが多いですね。離れて暮らす家族が支えるとなると、物理的距離がネックになりそうです。
まとめ:お金より、まず「仕組みを知る」が第一歩
介護は“いざ”というときに動くと、ほんとうに大変。でも、制度を知っているだけで、家計も気持ちもかなり軽くなります。
親のために使える制度を知って、「支え方の選択肢」を増やしておきましょう。
介護はひとりで背負わなくていい。仕組みをうまく使えば、親もあなたも安心して暮らせます。
参考リンク
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html - 厚生労働省「高額介護サービス費制度」
https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf - みんなの介護「家族介護慰労金」
https://www.minnanokaigo.com/news/kaigo-text/law/no59/

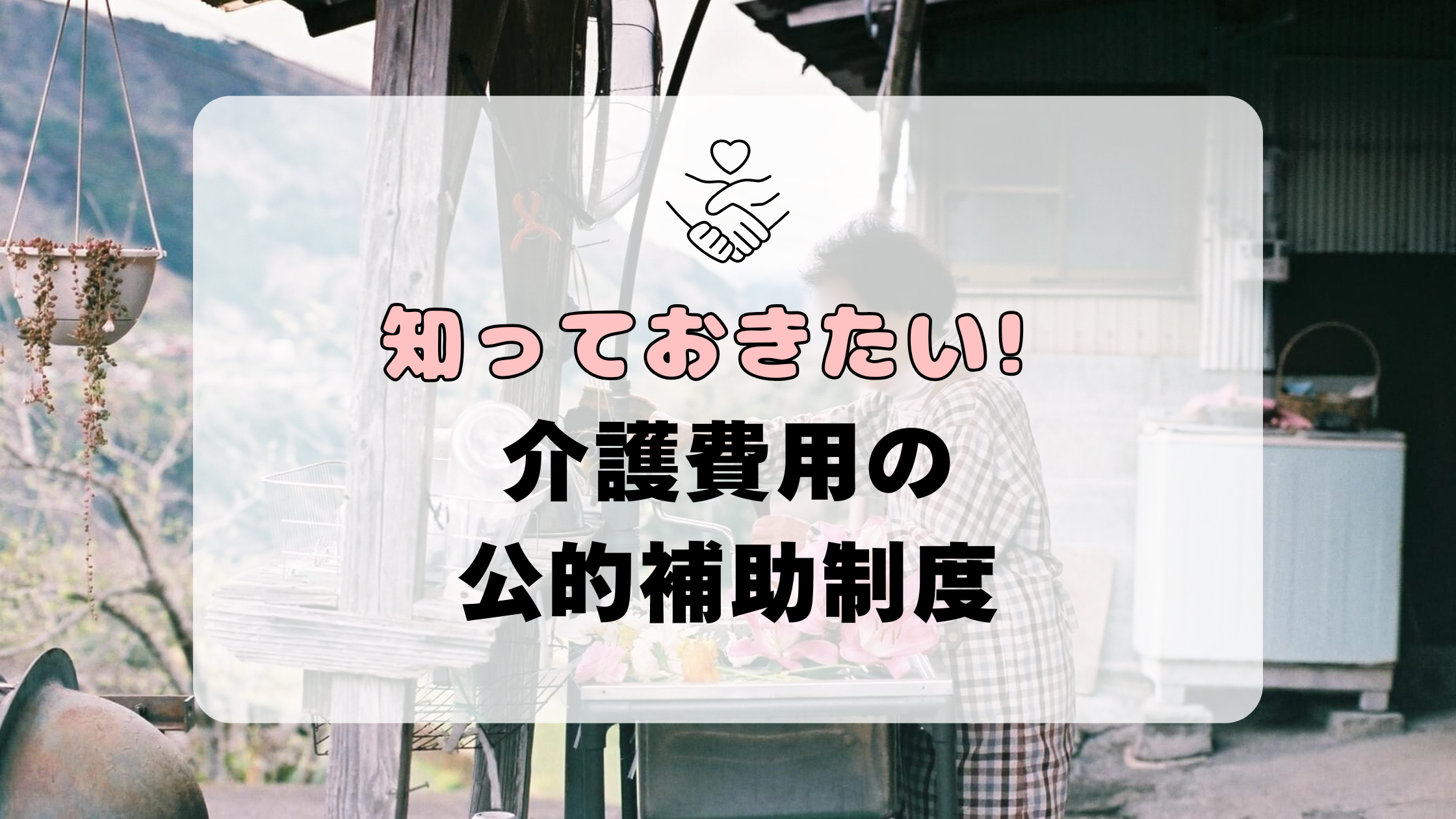
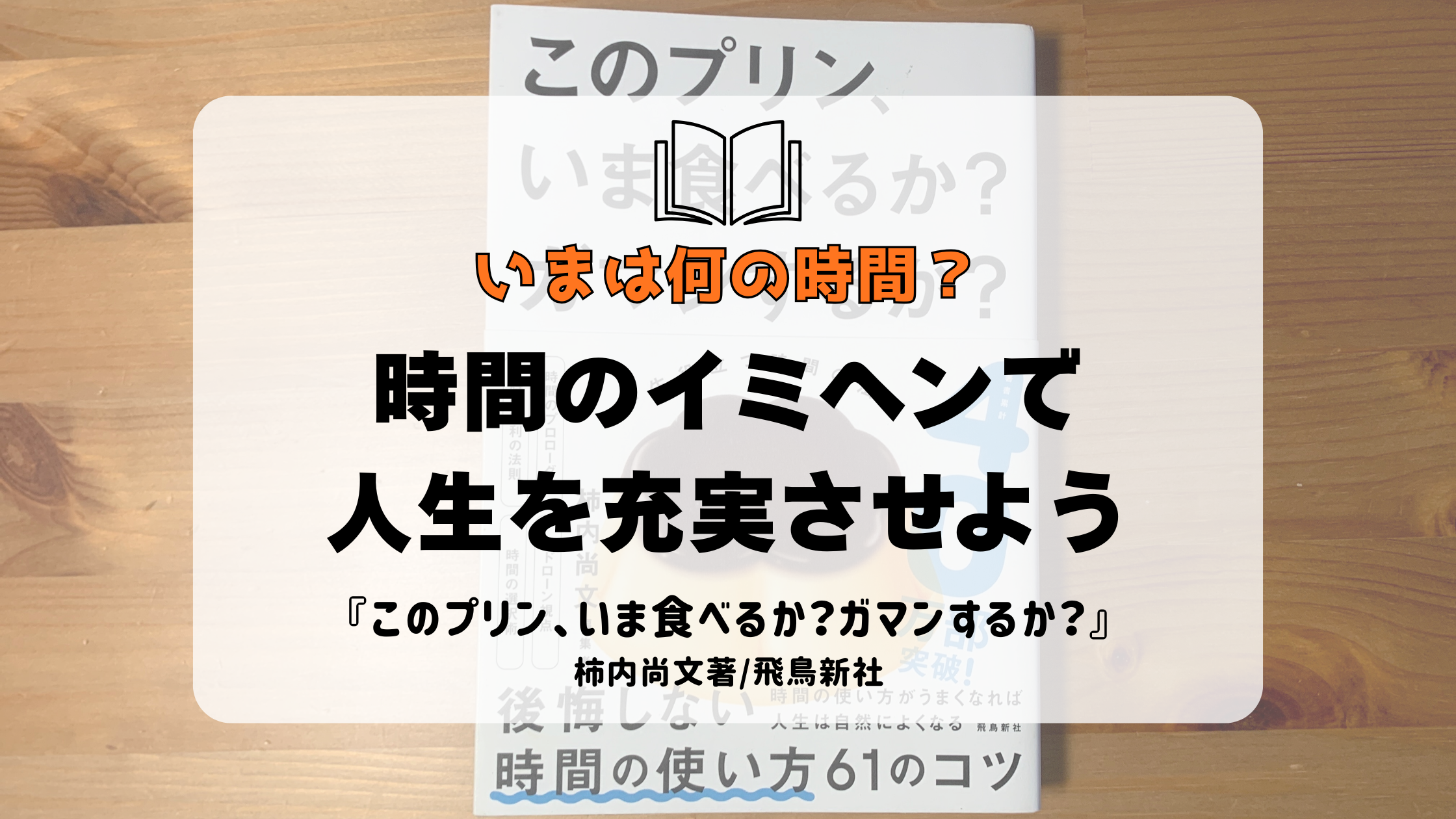
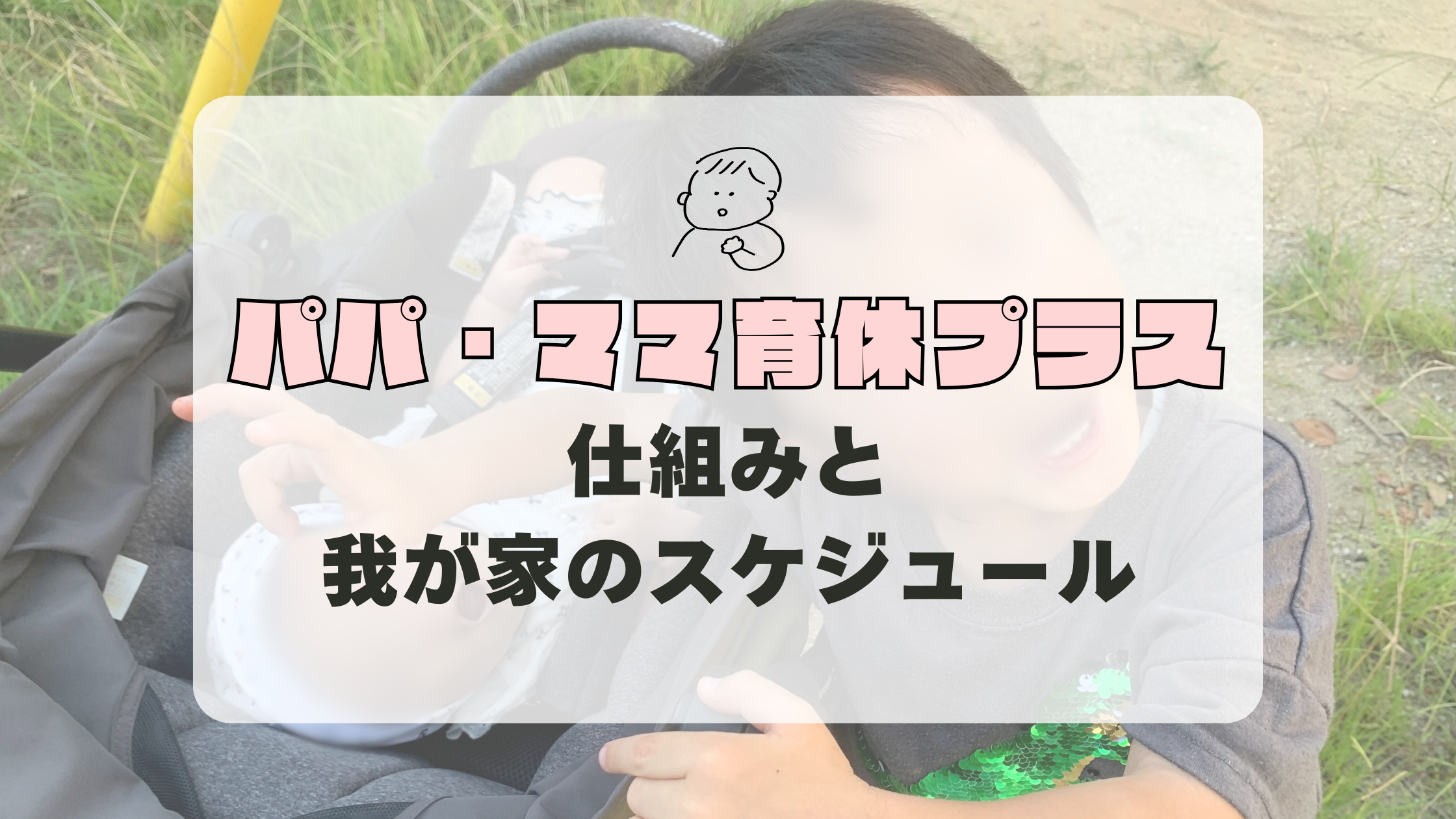
コメント