「特定重度生活習慣病保障特約って必要?」
最近よく聞くけれど、正直どんなときに使えるのか分かりづらいですよね。特約の仕組みを整理しつつ、実際にかかる治療費や、保険料を貯金・運用した場合の差もシミュレーションしてみました。
結論から言うと、「ある程度の貯金や医療保険があれば、無理につけなくても大丈夫」なケースが多いです。
特定重度生活習慣病保障特約とは?
簡単に言うと「生活習慣病の中でも、重い状態になったときに一時金がもらえる特約」です。
対象となる病気は保険会社によって違いますが、主に以下のようなケースが想定されています。
- がん(悪性新生物)
- 急性心筋梗塞
- 脳卒中(脳梗塞・脳出血など)
- 重度の糖尿病、腎疾患、肝疾患など
呼び方は会社によって少しずつ違っていて、「特定疾病保障特約」「三大疾病保険金特約」「重度生活習慣病特約」などとされています。
ただ、どれも“重い状態(働けない・長期治療が必要)”と診断されないと給付されません。
実際にかかる治療費は?
では、もし実際に生活習慣病になったら、どれくらいのお金が必要なのでしょうか。
ここでは代表的な3つの病気の例を見てみましょう(概算・自己負担3割の場合)。
| 病名 | 初期治療費の目安(自己負担分) | 入院期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 急性心筋梗塞 | 約20〜40万円 | 約2〜3週間 | ステント治療など含む |
| 脳卒中(脳梗塞・脳出血) | 約25〜50万円 | 約3〜4週間+リハビリ期間 | 後遺症リハビリ費が別途かかる |
| 重度の糖尿病(インスリン導入・合併症あり) | 約10〜20万円 | 約1〜2週間 | 継続的な通院・薬代あり |
これを見ると、「初期治療で20〜50万円あれば一旦対応できる」ことがわかります。
その後の費用は高額療養費制度によって月の自己負担上限(約8〜9万円程度)が設けられており、あとから払い戻しを受けられます。
つまり、一時的に立て替えるための50万円程度の貯金があれば、
ほとんどのケースで“経済的に詰む”ことは防げる計算です。
特約で受け取れる金額と比較してみる
特定重度生活習慣病保険特約の多くは、発症時に50〜100万円の一時金が受け取れます。
30歳、月1,195円・80歳までの保障なら、
1,195円 × 12か月 × 50年 = 717,000円を支払うことになります。
もしそのまま貯金・運用したら?
① 貯金として積み立てた場合
→ 72万円の原資がそのまま残ります。
② 利率5%で運用した場合
毎月1,195円を年5%で積み立てると、50年後にはおよそ 290万円 に。
(※複利計算・月利0.407%で算出)
つまり、保険に入らず積立・運用した方が、リスクに備えながら資産も増やせる可能性が高いです。
保険を「安心代」として考える
もちろん、「一時金がすぐ下りる」というスピード感は特約の強みです。もし共働きで休職リスクが不安な時期なら、一時的な安心代として付けておくのはアリ。
ただし、貯金ができる人・すでに医療保険で入院給付金がある人なら、特約を外してその分を運用に回す方が長期的には合理的です。
まとめ:必要かどうかは「貯蓄力」で判断
- 特定重度生活習慣病特約は、重い生活習慣病で一時金が出る保険
- ただし給付条件は厳しく、実際に使うケースは限定的
- 一時的な立て替え費用は50万円程度あれば多くのケースで対応可能
- 月1,195円を50年積立・年5%運用なら約290万円に
- 「安心代」としての価値を感じるかどうかで判断を
子育てや住宅ローン、教育費と“未来に向けた支出”が多い30代こそ、「保険で備えるより、貯めて備える」選択も現実的。
“安心の形”を見直すことが、じつは一番のリスク対策になるのかもしれません。

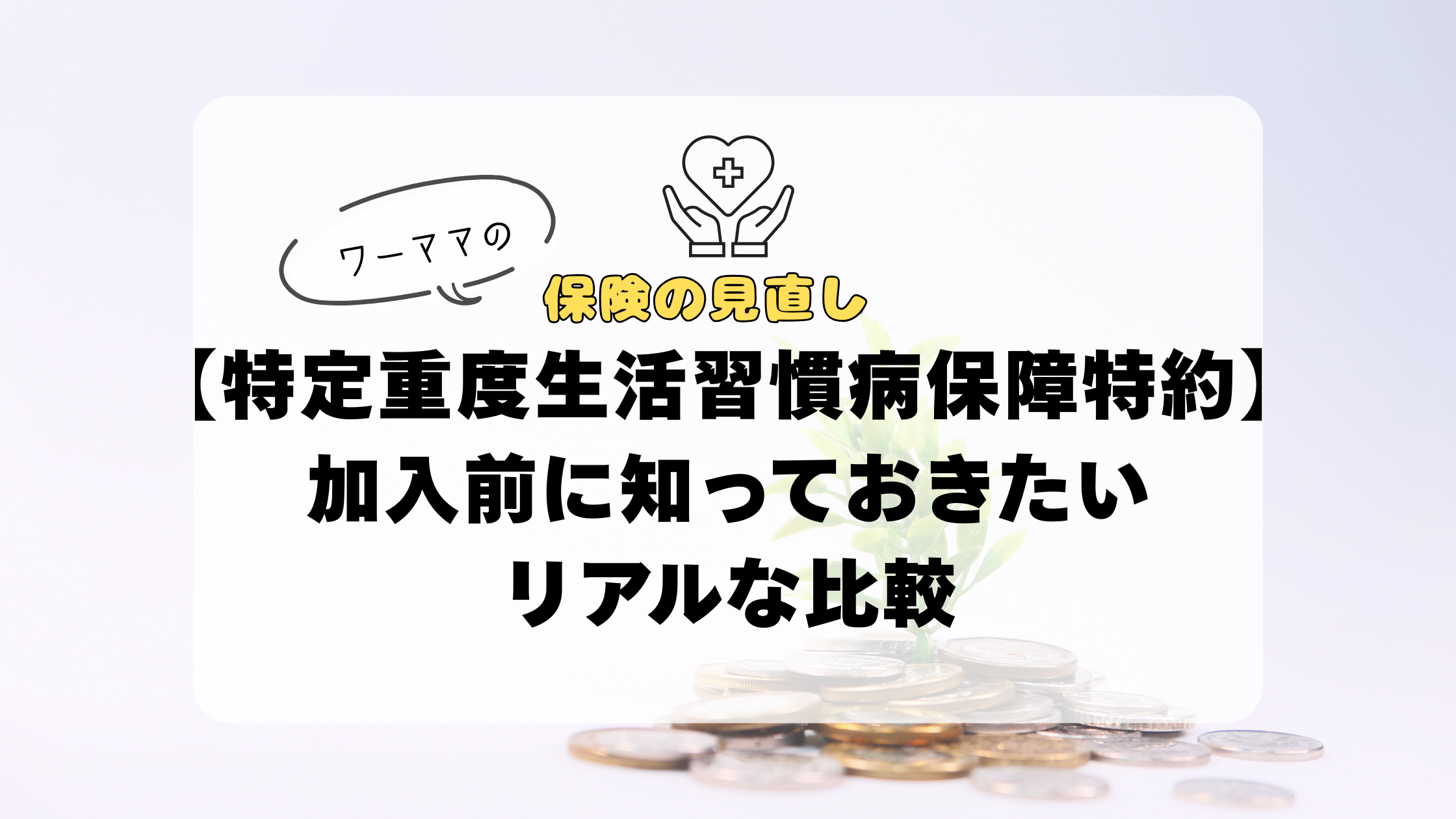
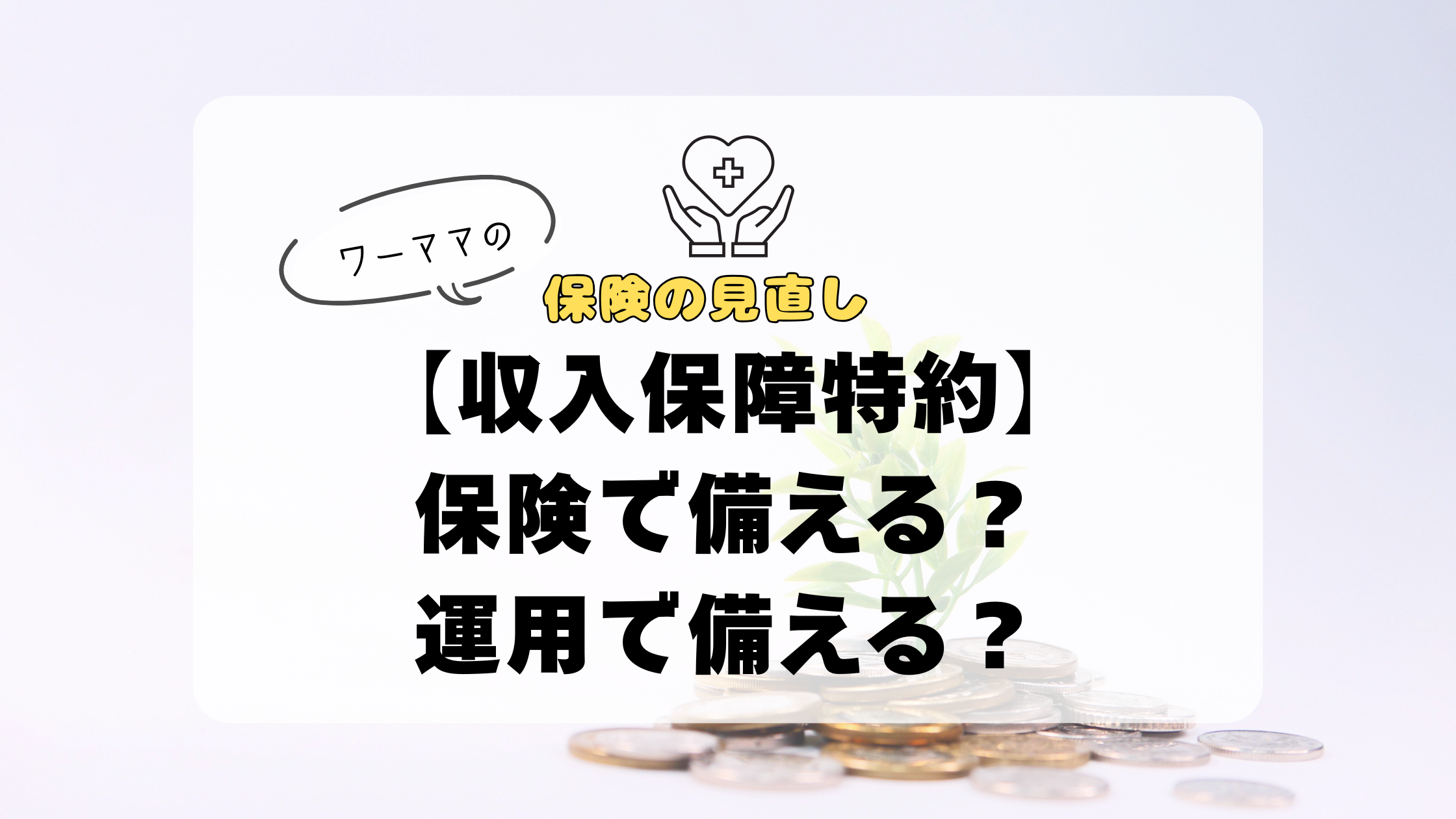
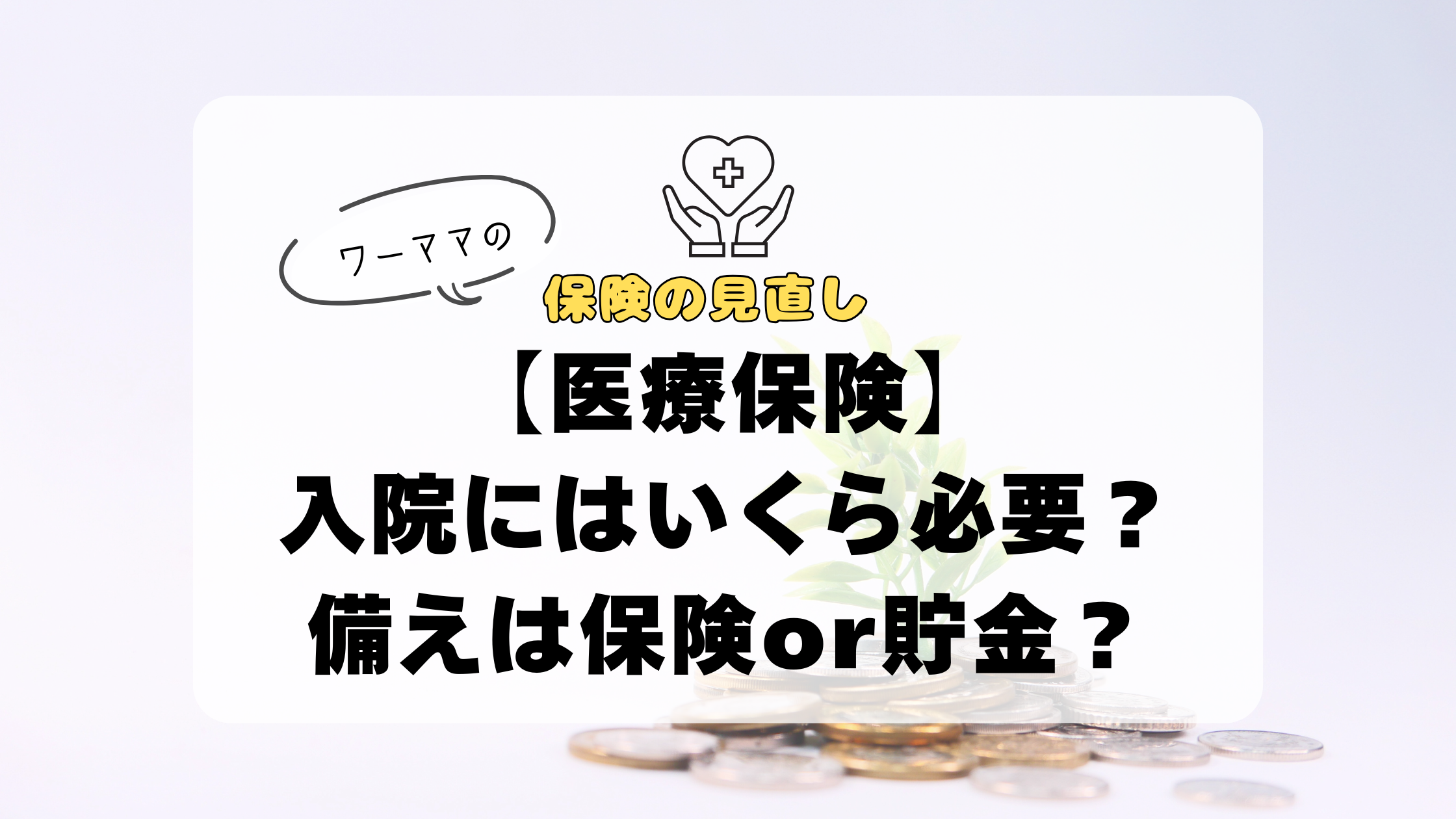
コメント