親から相続や贈与で受け継いだ果樹園。これから自分が住む予定がなかったり、次の世代に継がせるか迷うこともありますよね。

継いで事業を継続するのが分かりやすく「事業ごと継ぐ」方法ですが、そうはいかないケースも多いのではないでしょうか。

わたしも兄弟も地元を離れているので、果樹園の事業を「継ぐ」ことは簡単ではありません。
そんな『継げない』果樹園を、放置して荒らすのではなく、きちんと未来をデザインする終わり方はないのか。
この記事では、環境・文化・継承の3つの視点から、果樹園の終わり方を考えてみました。
あくまで個人で思いつく範囲での提案です。自然環境に悪影響を及ぼさぬよう、実行に際しては自治体の規制を確認したり、専門家の助言を得てください。
① 森林への再生(環境に返す方向)
結論
森林へ返すことで、土地を“次の命”につなぐ終わらせ方です。

理由
「人が入らなくても荒れない形」で終わらせたいなら、段階的な伐採+在来種の再生が効果的です。
放置ではなく、「植生遷移(しょくせいせんい)をデザインする」という発想です。
具体例
- 少しずつ果樹を伐り、コナラ・クヌギ・アカマツなど在来の木を残す
- 地元の林業組合に相談して、雑木林へ戻す再生活動を進める
- 行政の「森林環境譲与税」や「里山整備事業」などの補助制度を活用
これは単なる放棄ではなく、 “人の手で静かに閉じる” 選択です。
人が暮らした跡を、未来の自然に返す——そんな穏やかな終わり方です。

その土地に合った適切な森林管理が必要です。森林組合や自治体、その道に詳しい専門家に相談しましょう。
② ゆるやかな継承+記録を残す(家族の財産として残す方向)
結論
思い出や土地の物語を“形に残す”終わらせ方です。

理由
その土地に家族の記憶や地域とのつながりがあるなら、「終わらせ方を記録する」こと自体が、ひとつの継承になります。
残すのは土地だけでなく、“物語”や“記録”という文化資産です。
具体例
- 果樹をすべて伐らず、数本だけ「記念樹」として残し、家族や親族の農園として保持する
- 植生の変化を数年間観察・記録し、冊子にまとめる
- 柚子や栗の木材で、ベンチや看板など小さな作品をつくる
これは「継ぐ」でも「手放す」でもない “歴史を閉じて、次に委ねる” という再生のかたち。
家族の記憶を風景とともに残す、心にやさしい終わり方です。

農産物の生産を目的とした果樹園は終わりますが、親族が集える場所として残せると、家族にとっても意味のある財産ですね。
③ 譲渡・共有(手放す方向)
結論
土地を信頼できる第三者へ託す、現実的な終わらせ方です。
理由
遠方に暮らしていたり、維持管理の時間・費用が難しい場合、「引き継ぎ先を探す」ことがもっとも現実的な選択になります。
“預かってくれる人を探す” “買い取ってくれる人を探す” という発想です。
具体例
- 森林組合や地元自治体への寄付・譲渡
- 自然体験NPOや地域の自然学校への提供
- 農地バンクへの登録
- 企業のCSR活動の場として提供
立地が遠い場合は、安全管理だけ残してほぼ放置に近い運用も現実的です。人の手を離れても、自然や地域の手で活かされる土地に変わる可能性があります。

どれも条件が揃わないと実現可能性は低いです。まずは自分の地域で行われている民間の保全活動を調べてみると良いでしょう。
まとめ:終わり方にも、 “やさしさ” のデザインを
果樹園をどう終わらせるか——
それは、「自然に返す」「家族の財産として残す」「人に託す」という3つの道に整理できます。
どの選択も、放棄ではなく、未来へのバトン渡しです。

自然にも人にもやさしい終わり方を選ぶことが、これからの時代の “新しい相続” のかたちかもしれません。

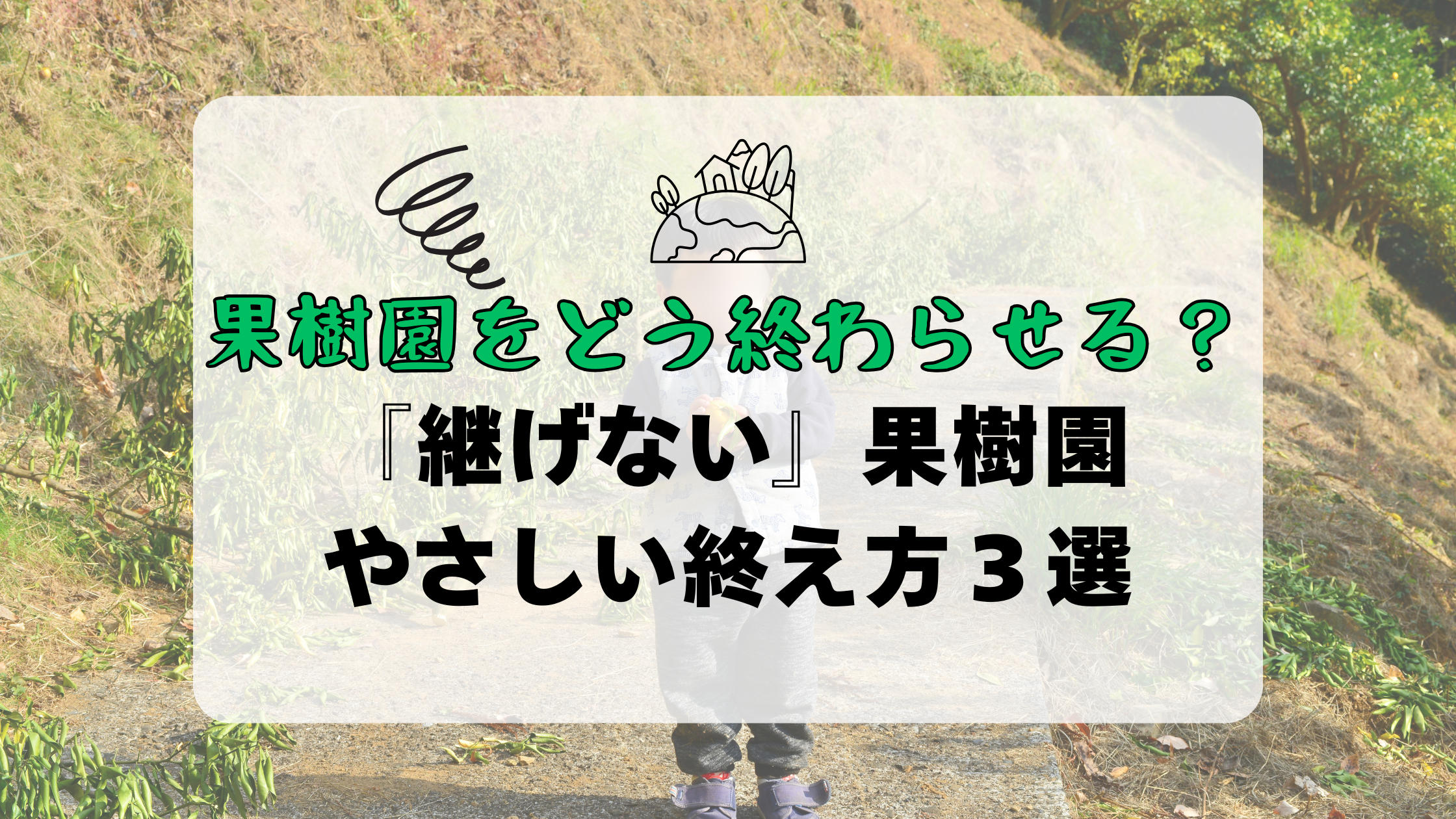
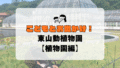
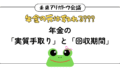
コメント