10月誕生月の夫。ねんきん定期便が送られてきて「こんだけしかもらえないのかよ~。払う金額の方が多いじゃんか。」ですって。
給与から差し引かれる税金や年金の額の大きさに毎度がっかりしている夫。額面が大きいほど引かれる額も大きくなって、余計に嫌になってしまうようです。
たしかに年金って、何歳まで生きれば回収できるのでしょう。
「ねんきん定期便で出てる額が、そのままポンと振り込まれるわけじゃない」ってことも意外と盲点。実際には手取りでどれくらい貰えるのでしょう。
今回は年金生活でかかるお金を整理して、 何歳まで生きれば納付分を回収できるか、本当の可処分はどれくらいか を考えてみたいと思います。
前提条件
今回は分かりやすいように以下の条件で話を進めたいと思います。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 加入期間 | 40年間(20〜60歳) |
| 年金受給開始 | 65歳から |
| 年金制度 | 厚生年金(会社員) |
| 保険料率 | 18.3%(会社と折半、本人負担9.15%) |
| 賞与など | 年収に含めてざっくり計算 |
| 備考 | 「生涯年収」は総支給額ベース(税や社会保険料控除前) |
年収別年金支給額(厚生年金+国民年金)
会社員の年金は 厚生年金(年収で変動)+国民年金(おおむね一律) で構成されています。
国民年金は20歳から60歳までのすべての人が加入する年金です。40年間所定の国民年金保険料を支払えば、満額の年金が受け取れます。
厚生年金の受給額は主に
「平均年収 × 加入年数 × 給付率」
で決まります。
現行の目安は
- 給付率:約0.55%/年(=加入1年ごとに“平均給与の0.55%分”が年金額になる)
- 加入期間:40年(20〜60歳で計算)
前提条件をもとに計算すると
厚生年金額 = 平均年収 × 0.0055 × 40 → 平均年収 = 厚生年金額 ÷ 0.22
という式で表されます。
年収別年金支給額(目安)
上記を踏まえ、年収ごとの年金支給額を算出すると以下のようになります。
| 年収 | 厚生年金 | 国民年金 | 年金額面 |
|---|---|---|---|
| 77万円 | 22万円 | 83万円 | 100万円 |
| 300万円 | 67万円 | 83万円 | 150万円 |
| 760万円 | 167万円 | 83万円 | 250万円 |
| 1,440万円 | 317万円 | 83万円 | 400万円 |
| 2,350万円 | 522万円 | 83万円 | 600万円 |
ねんきん定期便ではわからない “実際の手取り額”
定期便に“見込額”として出ている額は、確定額ではない
年金の加入実績・保険料納付実績・将来の年金見込額などを知らせる通知。毎年誕生日月に送られてきます。
現時点の加入実績をもとに、将来も現在の加入条件を継続したと仮定した場合の試算額が載るもの。実際の受給額は、加入期間・収入変動・制度改正などの影響を受けます。
また、その額がそのまま振り込まれるわけではなく、所得税や住民税、社会保険料(国保、後期高齢者医療保険、介護保険など)が差し引かれる可能性があります。
年金にかかる税金
年金=「雑所得」として所得税と住民税が課税されます。
でも、そのまま課税されるわけではなくて【公的年金等控除】+【基礎控除】を引いた残りの部分に所得税・住民税がかかります。
計算は ①公的年金等控除を引く → ②基礎控除を引く → ③残りに税率を適用 という順で行います。
計算の流れ(簡易版)
- 年金(1年間の受取り額)から「公的年金等控除」を引く。
- さらに「基礎控除(48万円)」を引く。
- 残った金額(=課税所得)に所得税をかける。
- さらに住民税(おおむね10%)をかける。
- 年金から税金を引いた残りが「手取り(可処分)」になる。
控除金額と税率(簡易版)
公的年金等控除のルール(簡略版)
- 年金が〜60万円 → 控除 = 年金(=全額非課税)
- 年金が60〜130万円 → 控除 = 60万円
- 年金が130〜410万円 → 控除 = 年金の25% + 27.5万円
- 年金が410〜770万円 → 控除 = 年金の15% + 68.5万円
- 年金が770万円超 → 控除 = 年金の5% + 145.5万円
(※税制は変わるので最終チェックは国税庁や市区町村で)
基礎控除:一律 48万円(年間)
所得税の速算表(主要部分)
- 課税所得 〜1,950,000円 → 税率 5%
- 1,950,001〜3,300,000円 → 税率 10%(速算控除 97,500円)
- 3,300,001〜6,950,000円 → 税率 20%(速算控除 427,500円)
(住民税は原則一律 10%)
では、具体例を5パターン、桁ごとに計算してみます。
(年金は「年間受給額」、税金は「年間の額」で計算します)
例1:年金 100万円 の場合
- 年金 = 1,000,000円
- 公的年金等控除 → 年金が100万円は「60〜130万円」の範囲 → 控除 = 600,000円
- 計算:控除 = 600,000円(決まった額)
- 課税対象 = 年金 − 公的年金等控除 − 基礎控除
= 1,000,000 − 600,000 − 480,000
= 1,000,000 − 1,080,000 = −80,000 → 0円(課税所得はマイナスなら0) - 所得税 = 0円、住民税 = 0円
- 手取り = 1,000,000 − 0 − 0 = 1,000,000円/年
→ つまり、年金100万円は非課税で、そのまま手元に残る。
例2:年金 150万円 の場合
- 年金 = 1,500,000円
- 公的年金等控除(年金が130〜410万の式)
控除 = 年金 × 25% + 275,000円
= 1,500,000 × 0.25 + 275,000
= 375,000 + 275,000 = 650,000円
(計算の内訳:1,500,000 × 0.25 = 1,500,000 ÷ 4 = 375,000) - 課税対象 = 1,500,000 − 650,000 − 480,000
= 1,500,000 − 1,130,000 = 370,000円 - 所得税(課税所得370,000は195万以下の5%)
= 370,000 × 0.05 = 18,500円
住民税 = 370,000 × 0.10 = 37,000円 - 合計税金 = 18,500 + 37,000 = 55,500円
- 手取り = 1,500,000 − 55,500 = 1,444,500円/年
→ 月だと約 120,375円(1,444,500 ÷ 12)
例3:年金 250万円 の場合
- 年金 = 2,500,000円
- 公的年金等控除(年金が130〜410万の式)
= 2,500,000 × 0.25 + 275,000
= 625,000 + 275,000 = 900,000円 - 課税対象 = 2,500,000 − 900,000 − 480,000
= 2,500,000 − 1,380,000 = 1,120,000円 - 所得税(課税所得1,120,000 は195万円以下 → 5%)
= 1,120,000 × 0.05 = 56,000円
住民税 = 1,120,000 × 0.10 = 112,000円 - 合計税 = 56,000 + 112,000 = 168,000円
- 手取り = 2,500,000 − 168,000 = 2,332,000円/年
→ 月だと約 194,333円
例4:年金 400万円 の場合
- 年金 = 4,000,000円
- 公的年金等控除(年金が130〜410万の式)
= 4,000,000 × 0.25 + 275,000
= 1,000,000 + 275,000 = 1,275,000円 - 課税対象 = 4,000,000 − 1,275,000 − 480,000
= 4,000,000 − 1,755,000 = 2,245,000円 - 所得税(2,245,000は195万超〜330万以下の範囲 → 税率10%、速算控除97,500円)
= 2,245,000 × 0.10 − 97,500
= 224,500 − 97,500 = 127,000円
住民税 = 2,245,000 × 0.10 = 224,500円 - 合計税 = 127,000 + 224,500 = 351,500円
- 手取り = 4,000,000 − 351,500 = 3,648,500円/年
→ 月だと約 304,042円
例5:年金 600万円 の場合
- 年金 = 6,000,000円
- 公的年金等控除(410〜770の式)
= 年金 × 15% + 685,000円
= 6,000,000 × 0.15 + 685,000
= 900,000 + 685,000 = 1,585,000円
(計算:6,000,000 × 0.15 = 6,000,000 × 15% = 900,000) - 課税対象 = 6,000,000 − 1,585,000 − 480,000
= 6,000,000 − 2,065,000 = 3,935,000円 - 所得税(3,935,000 は 3,300,001〜6,950,000 の範囲 → 税率20%、速算控除 427,500円)
= 3,935,000 × 0.20 − 427,500
= 787,000 − 427,500 = 359,500円
住民税 = 3,935,000 × 0.10 = 393,500円 - 合計税 = 359,500 + 393,500 = 753,000円
- 手取り = 6,000,000 − 753,000 = 5,247,000円/年
→ 月だと約 437,250円
年間年金 “手取り” 概算まとめ
上記をまとめると以下のようになります。
| 年金額面 | 手取り年金 | 徴収される税金等 |
|---|---|---|
| 100万円 | 100万円 | 0万円 |
| 150万円 | 144万円 | 6万円 |
| 250万円 | 233万円 | 17万円 |
| 400万円 | 365万円 | 35万円 |
| 600万円 | 525万円 | 75万円 |
だいたい 額面×0.87 くらいですね。
注意点
- 上の計算は 税金だけ(所得税+住民税)を扱ったもの。
実際の年金生活では 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 等がかかることが多いです。これらも手取りを減らすので、最終的な「使えるお金」はさらに少なくなります。 - 課税の仕組みは「合算」されます。年金以外に収入(不動産収入・アルバイトなど)があると、合算して課税されます。雑所得なので損益通算は雑所得(仮想通貨など)内に限られます。
- 住民税の軽減や、所得税の年末調整・医療費控除、配偶者控除などで変わる場合があります。
- 自治体によって保険料の計算方法や税額が少し違うので、住んでいる市区町村での確認が必要です。
納付分いつ回収できる?
じゃあ、納付したお金をいつ回収できるんですか、という話。
生涯年収別・支払う年金保険料の目安(本人負担分)
年収がずっと40年間同じと仮定した場合の本人負担額概算は以下の通りです。
| 年収 | 厚生年金 年間本人負担 | 国民年金 年間本人負担 | 40年間の合計(本人負担) |
|---|---|---|---|
| 77万円 | 約7万円 | 約21万円 | 約1,120万円 |
| 300万円 | 約28万円 | 約21万円 | 約1,960万円 |
| 760万円 | 約70万円 | 約21万円 | 約3,620万円 |
| 1,440万円 | 約132万円 | 約21万円 | 約6,120万円 |
| 2,350万円 | 約215万円 | 約21万円 | 約9,440万円 |
※本人負担は「年収 × 9.15%」、会社負担を含めると「年収 × 18.3%」で計算。
(実際には賞与や加入年数により多少前後します)
補足
- 実際には途中で収入が上がるので、平均年収が生涯年収÷40よりやや高くなります。
- 自営業(国民年金)だと負担はもっと少なく、40年間で約800万円ほど(ただし受給額も少ない)。
年収別回収期間イメージ
まとめると以下のようになります。
| 生涯年収 | 本人が払う年金保険料総額 | 受け取る年金(目安) | 回収期間 |
|---|---|---|---|
| 77万円 | 約1,120万円 | 約100万円/年 | 11年強で元取れる |
| 300万円 | 約1,960万円 | 約150万円/年 | 13年 |
| 760万円 | 約3,620万円 | 約250万円/年 | 15年弱 |
| 1,440万円 | 約6,120万円 | 約400万円/年 | 16年弱 |
| 2,350万円 | 約9,440万円 | 約600万円/年 | 16年弱 |
所得税、住民税を考慮すると、実際の手元に戻ってくる期間は上記より若干伸びるでしょう。
自分たちのケースにあてはめ、公的年金シュミレーターでの年金額で、保険料の回収までにかかる年数を割り出すと…
私の場合
・60歳から受給…20年(80歳)
・65歳から受給…15年3か月(80歳)
夫の場合
・60歳から受給…22年11か月(82歳)
・65歳から受給…17年5ヶ月(82歳)
上記表と年収帯はやや違っていますが、65歳受給でおおむね15年~17年はかかりそうなイメージであることにちがいはありません。
つまり、80歳以降まで長生きしなければ元が取れない!※カエ子調べ
日本人の平均寿命は令和6年時点で 男性81歳、女性87歳です。
少なくとも平均寿命程度は生きねばなりませんね。
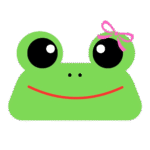
年収額が大きいほど、長生きしなくちゃ元が取れない構造だとわかります。稼ぐ人/働く人で支えられている年金なのですね。
まとめ
- ねんきん定期便に書かれている年金見込額はあくまで試算値
- 所得税や住民税、保険料が差し引かれるので、見かけの額より手取りは減る
所得税・住民税差し引き後の手取りは 額面×0.87 くらい - 納付保険料を回収できる期間は人によって違う。年収が大きいほど回収までに期間が必要な可能性あり。
- 納付保険料の回収に15~17年かかる。年金の繰り上げ受給をした場合は20年以上かかる。
- どちらにせよ、80歳以降まで生きなければ納付保険料の回収は出来ない可能性が高い。
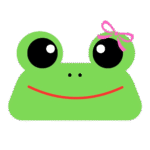
国民年金のみだと10年ほどで回収できそうです。
年金保険は長生きラッキー保険です。頑張って生きている今の自分のためにも、健康に長生きせねばなりませんね。

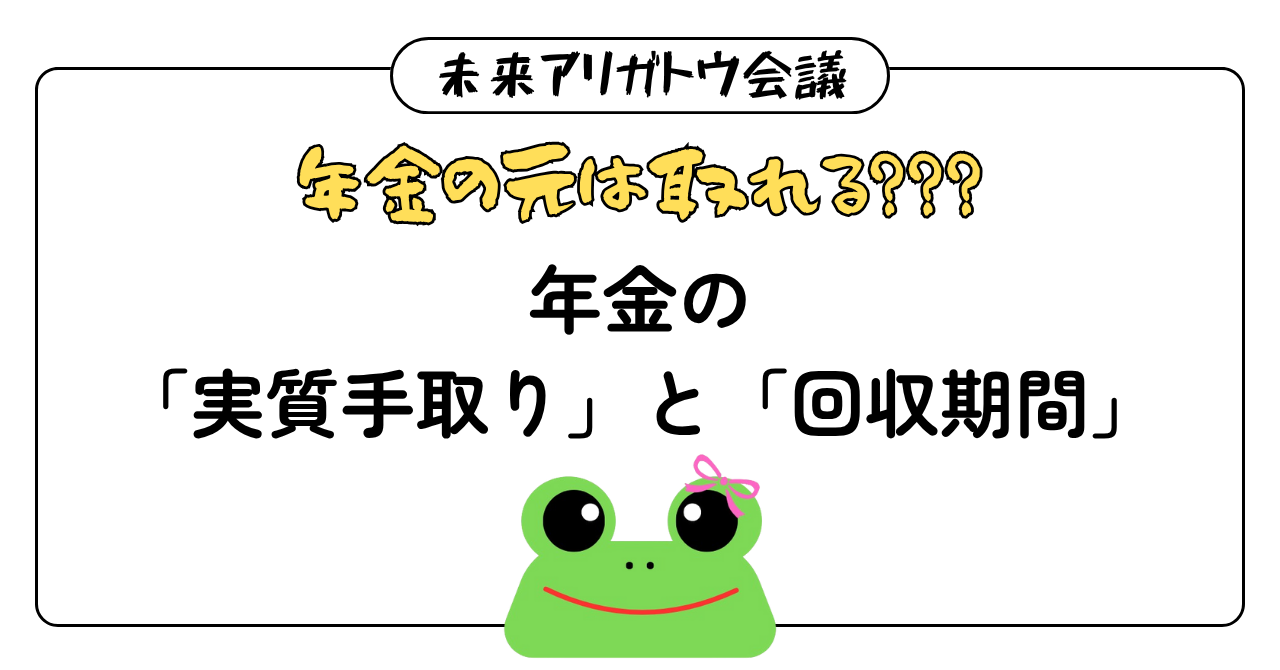
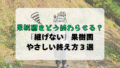
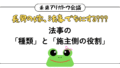
コメント