最近、全国各地でクマの出没がニュースになっています。
SNSでは「山にエサがないから」「温暖化でどんぐりが不作だから」「太陽光パネルができたから」といった声をよく見かけます。それらは主要な要因であると思いますが、実際のところ、それだけでは説明できません。
大きな要因のひとつに、人と自然の“あいだ”にあった「里山の機能」が失われつつあることがあります。
里山とは、山と街をつなぐ緩衝帯のような存在でした。人が薪を取ったり、果樹を育てたり、畑を手入れしたりすることで、動物たちが「ここから先は人の領域」と認識できる境界が維持されていたんです。
しかし、高齢化や後継者不足で管理が行き届かなくなると、果樹が実を落とし放題になり、雑草や竹が繁茂し、動物たちにとって安全で食料豊富な場所になってしまいます。
この「人の手が抜けた空間」こそが、クマやシカが人里へ近づくきっかけの一つになっています。
私の実家も例外ではありません
私の実家は、山間部にある柚子と栗がメインの果樹園です。

斜面地に広がる畑は手入れが大変で、近年は高齢の親だけで維持するのが難しくなってきました。近隣の家庭も同様の事象が起こっています。もしこのまま放置すれば、いずれ草木に覆われ、野生動物の通り道になってしまうでしょう。
「もう誰も継がない土地をどう終わらせるか」は、今の日本の地方が抱える共通の課題でもあります。
放棄せず、“終わらせる”という選択
果樹園や農地をそのまま放置せず、“終わらせてから引き渡す”ことが大切です。終わらせるとは、単に伐採して更地に戻すことではありません。「生態的・社会的に中立な状態に戻す」ことです。
実家のような急斜面の果樹園の場合、具体的には以下のようなアクションが考えられます。
- 果樹の計画的な伐採と抜根
高木果樹(栗など)は放置すると実が落ちて野生動物の餌になります。
伐採後は切り株を抜根し、再萌芽を防ぐ処理を行います。 - 斜面の侵食防止のための植生回復
裸地化を防ぐため、根を張る在来草本(チガヤやヨモギなど)や低木(ヤマツツジなど)を導入します。地域の森林組合や環境事務所が推奨する在来種の緑化計画を参考にするのが安心です。
※遺伝子レベルの多様性維持のため、その土地で採取された樹種の使用を行うことが望ましい - 動物侵入防止柵の設置
山側の獣道を中心に、ワイヤーメッシュや電気柵を設置します。補助金(農地・森林保全整備事業)を利用できるケースもあります。 - 地域単位での「里山再デザイン」
個人で土地を守りきれない場合、周辺の空き農地とまとめて「地域協定地」として再生する方法もあります。林野庁の「里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金」では、地元団体・自治体・土地所有者が連携して、景観と生態系を維持する活動に補助が出ます。
境界をもう一度、デザインする時代へ
人と動物の関係は、対立ではなく距離のデザインです。
人的被害が多発する中でクマを追い払うことは急務を要します。それに加えて「人の暮らしが動物たちへのメッセージになる状態をどう作るか」を考える必要があります。そのための実践が、里山の再生活動であり、(農地を・放置を)終わらせる勇気です。
誰かが耕していた場所を「ただの空き地」にせず、「命の循環が続く場」として引き継ぐこと。それが次の世代にとっての、本当の“財産”になるのだと思います。

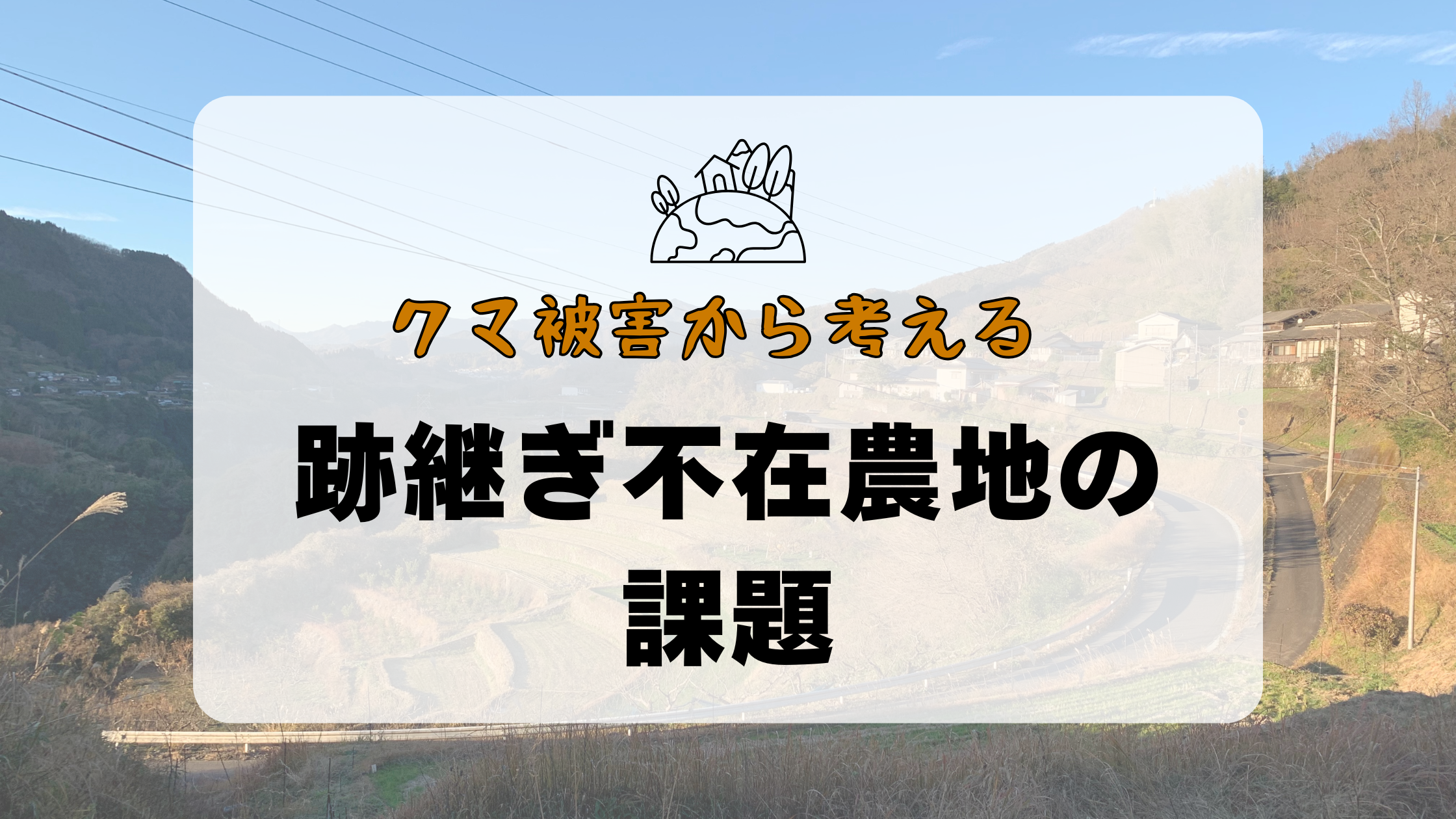
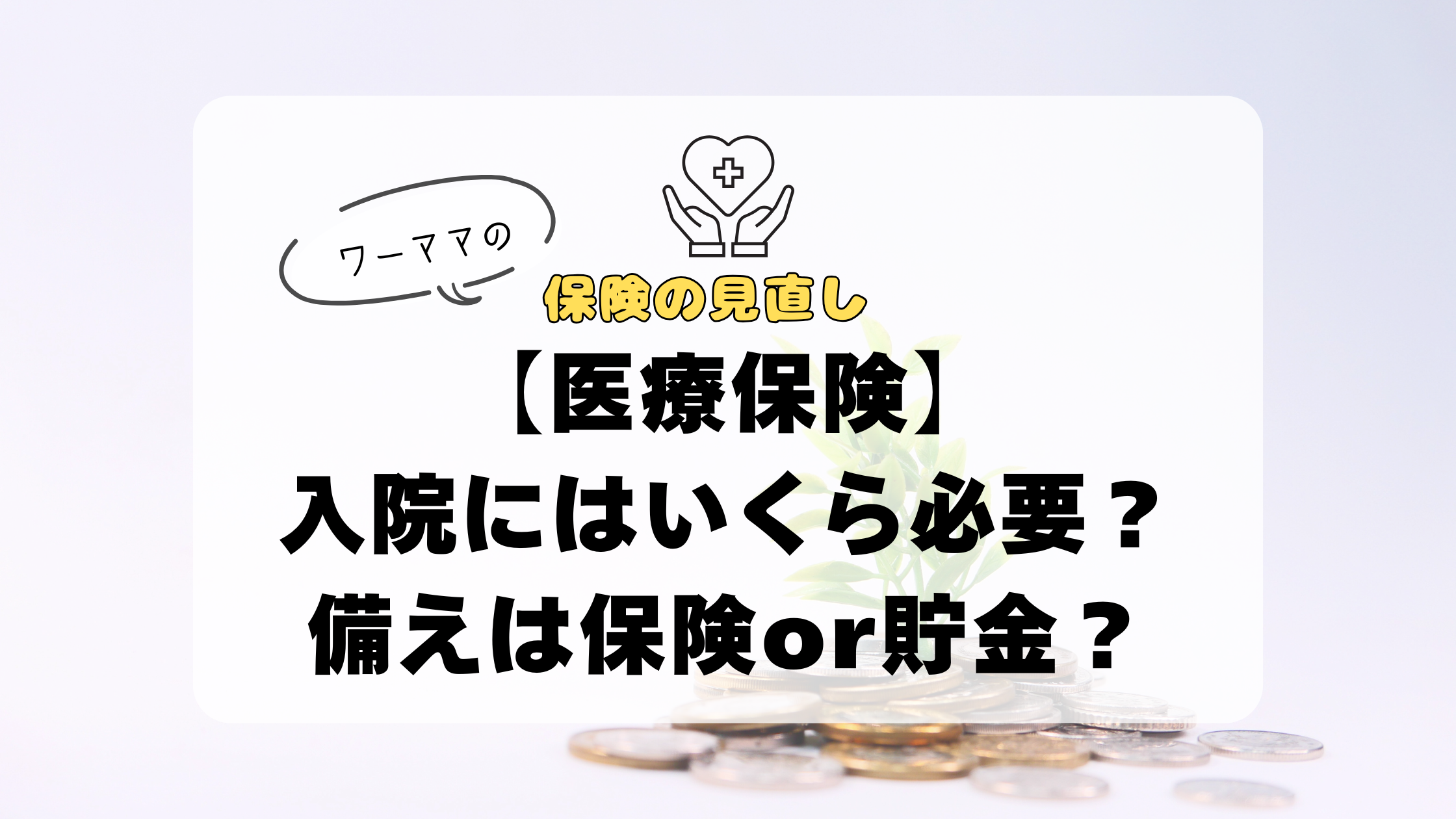
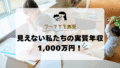
コメント