経済ニュースやマーケットレポートでよく耳にする「GDP」「日銀短観」などの指標。これらは日本経済の“健康診断結果”のようなもので、投資判断や政策の方向性を考えるうえで欠かせません。
ここではCFP対策を兼ねて、主要な経済指標をテーマ別に整理します。
① GDP(国内総生産)
意味: 一定期間に国内で生み出された付加価値の合計。日本経済の「大きさ」を表す指標。
公表: 内閣府(四半期ごと)
ポイント:
- 名目GDPは「物価変動を含む」金額、実質GDPは「物価変動を除いた」数量ベース。
- 前期比・年率換算の伸び率が景気の拡大・後退を判断する基本。前期比増加率を「経済成長率」という。
- 3面等価の原則:生産(生産したモノやサービスの合計)・分配(給与・利益)・支出(消費・投資・輸出など)の3つの値は等しくなる、という法則。実際にはそれぞれの統計手法の違いから一致しない。
- 寄与度:GDPに対する各需要項目の増加額割合。例)去年よりGDPが2%増えたとして、個人消費が+1%分押し上げた・輸出が+0.8%押し上げた・公共投資が+0.2%押し上げた、「どの要素が成長に貢献したのか」。
- 寄与率:GDPの増加額に対する各需要項目の増加額割合。
- GDPギャップ:今の日本が“本気を出したときの実力”よりどれくらい上か・下かを示す差。実際のGDPが潜在GDPを下回るときのギャップを「デフレギャップ」、上回るときを「インフレギャップ」という。一般的にデフレギャップはデフレーションを、インフレギャップはインフレーションを引き起こす要因となる。
GDP関連の算式
| 指標名 | 算式 | 意味・ポイント |
|---|---|---|
| 名目GDP | 各年の「物価 × 生産量」を合計 | 実際の市場価格で測った国内の生産額。物価変動の影響を含む。 |
| 実質GDP | 名目GDP ÷ 物価指数 × 100 | 物価変動を取り除いた「実際の生産量の変化」を見る。景気実態を測る指標。 |
| 名目経済成長率 | (当年の名目GDP − 前年の名目GDP) ÷ 前年の名目GDP × 100 | 物価変動も含めた成長率。インフレで高く見えることもある。 |
| 実質経済成長率 | (当年の実質GDP − 前年の実質GDP) ÷ 前年の実質GDP × 100 | 物価の影響を除いた「実質的な経済の伸び率」。景気判断に使われる。 |
| GDPデフレーター | 名目GDP ÷ 実質GDP × 100 | 物価水準の変化を示す。上昇=インフレ、低下=デフレ傾向。 |
| GDP成長率(年率換算値) | (四半期の実質GDP成長率+1)⁴ − 1 | 四半期成長を「1年分に換算」した数値。四半期GDP速報で使われる。 |
② 景気動向指数(CI・DI)
意味: 景気の現状・方向性を把握するための複合指数。
公表: 内閣府(毎月)
構成: 先行指数・一致指数・遅行指数の3つ。
ポイント:
CI(コンポジット・インデックス)
景気変動の大きさやテンポを表す指数。経済の“実測データ”を使った景気のスコア表のようなもの。指数が100を超えると景気が基準期より良いとされる。
「一致指数」は現在の景気、「先行指数」は数か月後の景気を示唆。
| 種類 | 内容 | 天気でいうと |
|---|---|---|
| 先行指数 | 数か月先の景気を先読み | 株価・受注など |
| 一致指数 | 今の景気そのもの | 生産・出荷など |
| 遅行指数 | 景気が変わった後に動く | 雇用・賃金など |
指数が「100より上」なら基準期より景気が良い、「100より下」ならちょっと弱め、という目安。
DI(ディフュージョン・インデックス)
景気が良くなっている動きがどのくらいの分野に広がってるか?を数字で表したもの。DIは、「景気が上向いている会社・業界の“数の割合”」を見るイメージ。なので、景気ウォッチャー調査でも日銀短観でも、DIの形で結果を出す。
指数が「50より上」なら 改善している業種のほうが多い(景気拡大)、「50より下」 なら 悪化している業種が多い(景気後退)。
③ 景気ウォッチャー調査
意味: 街角の現場感を反映する調査(小売・飲食・サービス業など)。
公表: 内閣府(毎月)
ポイント:
- 調査対象は実際に経済活動を行う“現場の声”。アンケート方式で調査を実施。
- DI(Diffusion Index)が50を超えると景気が「良い」と感じる人が多い。
④ 日銀短観(全国企業短期経済観測調査)
意味: 全国の企業に対する業況判断調査。企業心理を表す。
公表: 日本銀行(年4回、3・6・9・12月)
ポイント:
- 大企業製造業DIがプラスなら「景況感が良い」企業が多い。
- 設備投資計画や雇用見通しなども重要なサブ指標。
- 業状判断DI=「良い」と回答した企業割合ー「悪い」と判断した企業割合
⑤ 機械受注統計
意味: 企業が新たに機械を発注した額。設備投資の先行指標。
公表: 内閣府(毎月)
ポイント:
- 特に「民需※1(船舶・電力を除く)」が先行指数として注目される。
- 増加傾向は生産拡大や景気回復の兆し。
- 月次の数値は振れ幅が大きいため、移動平均値か四半期ベースで比較することが一般的。
※1:「民需」=民間(つまり政府以外)の人や企業がつくり出す需要のこと。反対語は「公需(こうじゅ」=政府や自治体による公共事業や支出。
⑥ 鉱工業指数
意味: 製造業などの生産活動を示す指標。
公表: 経済産業省(毎月)
ポイント:
- 生産・出荷・在庫の3つの系列で構成。
- 「生産指数」はGDPの動きとも連動性が高い。
⑦ 在庫循環
意味: 生産と在庫の関係から景気の循環局面を分析。
ポイント:
- 一般に「在庫積み増し→調整→減少→再積み増し」で1サイクル。
- 過剰在庫は生産調整→景気後退を示唆。
- キチンの波:在庫循環に起因するといわれる景気循環のサイクル
| 名前 | 周期 | 原因 |
|---|---|---|
| キチンの波 | 約3〜4年 | 在庫調整などの短期要因 |
| ジュグラーの波 | 約7〜11年 | 設備投資の更新サイクル |
| クズネッツの波 | 約15〜25年 | 住宅や建設投資の周期 |
| コンドラチェフの波 | 約40〜60年 | 技術革新や大きな構造変化 |
在庫循環の4つの局面
経済アナリストがよく使う在庫循環図は、グラフで4つの局面に分かれています。
- 在庫積み増し局面(回復期)
→ 売上が伸びて、生産を増やして在庫も少しずつ増やす。
「景気が回復してきた!」タイミング。 - 在庫過剰局面(過熱期)
→ 作りすぎて在庫が多すぎる。売れ残りが出る。
「そろそろ景気のピーク?」な時期。 - 在庫調整局面(後退期)
→ 在庫が多いから生産を減らす。景気が冷え込む。 - 在庫減少局面(底打ち期)
→ 売れて在庫が減ってきた。生産を再開する。
「次の回復に向けた助走」期。
⑧ 稼働率・稼働率指数
意味: 設備がどれくらい稼働しているかを示す指標。
公表: 経済産業省(毎月)
ポイント:
- 高い稼働率=需要が旺盛、低下=景気減速の兆候。
- 鉱工業生産指数と併せて判断。
⑨ 設備投資比率
意味: 企業収益に対する設備投資額の割合。
ポイント:
- 中期的な経済トレンドを示す指数。
- 設備投資の拡大は将来の成長期待を反映。
- 企業の「攻め」姿勢を測る目安。
⑩ 家計・消費関連統計
代表指標: 家計調査、家計貯蓄、家計貯蓄率、消費動向指数、小売販売額など。
公表: 総務省、経産省ほか
ポイント:
- 実質消費支出の増減は個人消費のトレンドを示す。
- ボーナス期や物価変動の影響に注意。
家計調査(総務省)
日本中の家庭がどんなものにお金を使っているかを調べた調査。総務省が毎月、全国約9,000世帯の「収入・支出・貯蓄・借金」などを細かく集計。
たとえば、
- 食費はいくら?
- 教育費はどれくらい?
- ボーナスは何に使った?
といったリアルな生活のデータをもとに、景気の“肌感”を数字にしてくれます。
を数字にしています。
→ ニュースで「家計調査によると、実質消費支出は前年同月比−2%」と出たら、それは「一般家庭の消費が減っている=景気の勢いが落ちてる」という意味。
家計貯蓄(日銀)
家庭が持っている貯金や保険、株などの金融資産の合計額。内閣府が公表する国民経済計算をもとに日銀がまとめていて、日本全体の“家のお金の体力”を示します。
たとえば、
- 現金や預金
- 保険(生命保険など)
- 株や投資信託
などが含まれます。
→ 要するに「みんなの財布の中身+タンス貯金+投資口座」を全部足したもの。
家計貯蓄率
これは「収入のうち、どれくらいを貯金に回したか」をパーセントで表した数字。
たとえば、月の手取りが30万円で、そのうち3万円を貯金したら、家計貯蓄率=10%。
国全体でみると、
家計貯蓄率が高い → みんな将来に備えて貯めてる(消費が控えめ)
家計貯蓄率が低い → 貯金せずに使ってる(消費が活発)
→つまり、貯蓄率の変化を見ると、景気の「慎重ムード」か「前向きムード」かがわかる。
消費動向指数(消費者態度指数・内閣府)
家計調査が“実際のデータ”なのに対して、“気持ち(マインド)”を測る調査。
内閣府が全国の世帯に
「暮らし向き」「収入の増え方」など今後半年の見通しを5段階で評価するアンケートをし、結果を指数化しています。
指数が50を上回ると「楽観的」、50を下回ると「悲観的」と判断されます。先行きに対する消費マインドが反映されることから、「先行指数」に採用されています。
→ つまり、消費動向指数は“お財布のひもを締めるか、緩めるか”の心理バロメーターです。
小売販売額(商業動態統計・経産省)
これは、実際にお店でどれだけモノが売れたかを表す統計。経済産業省が毎月発表しています。
スーパー、コンビニ、百貨店、ネット通販などの販売データを集めて、
「日本の消費の勢い」をつかむのに使います。
たとえば、
小売販売額が前年比+5%→ モノがよく売れてる=景気が上向き
小売販売額が−3%→ 消費が冷え込み気味
と読み取ることができます。
まとめると
| 指標 | 内容 | タイプ |
|---|---|---|
| 家計調査 | 家計の“実際の支出と収入”を調べる | 実績データ |
| 家計貯蓄 | 家計が持っている資産の総額 | 実績データ |
| 家計貯蓄率 | 収入のうち貯蓄に回した割合 | 行動データ |
| 消費動向指数 | 「買いたい気分」をアンケートで測る | 心理データ |
| 小売販売額 | お店で実際に売れたモノの金額 | 実績データ |
こうやって並べて見ると、「家計調査」や「小売販売額」は現実の動き、「消費動向指数」は気持ちの動きを表していることがわかります。
景気分析ではこの2つのズレ(気持ちは前向きだけど、実際の消費はまだ、のような)を読むのがポイント。
⑪ 雇用関連統計
代表指標: 有効求人倍率、完全失業率、雇用者数。
公表: 厚生労働省、総務省
ポイント:
- 有効求人倍率が1を超えると「求人>求職」で人手不足気味。
- 失業率の改善は景気回復の遅行指標。
完全失業率(総務省・労働力調査)
これは文字どおり、仕事をしたいけど働けていない人の割合。
完全失業率=(失業者 ÷ 労働力人口)×100
たとえば、仕事をしている or 求職中の人が6,000万人いて、そのうち180万人が失業しているなら、完全失業率=3.0%になります。
ポイント
- 完全失業者=「働く意思と能力があり、求職活動をしているが仕事がない人」
- ニートや専業主婦は含まれません。
→つまり、“働きたいのに働けていない”人がどれだけいるかを見る指標です。
景気の動きに遅行する傾向があり、景気動向指数の「遅行系列」に採用されています。
読み方の目安
- 3%以下 → 景気が良く、雇用が安定している
- 5%以上 → 不況のサイン(企業が採用を減らしている)
日本は近年、2〜3%台で推移していて、実は世界的に見てもかなり低い水準。つまり「雇用が堅い=景気の下支えが強い」と言えます。
有効求人倍率(厚生労働省・職業安定業務統計)
ハローワークに登録されている「求人数」と「求職者数」のバランスを示す数字です。
有効求人倍率=求人数 ÷ 求職者数
たとえば、求職者100人に対して求人が120件あれば、有効求人倍率=1.2倍。
産業別にも算出されており、産業別のニーズを把握することができます。
読み方の目安
- 1.0倍 → 求人数と求職者数が同じ
- 1.0超 → 仕事のほうが多い(人手不足ぎみ)
- 1.0未満 → 求職者のほうが多い(不況気味)
→つまり、企業がどれだけ“人を欲しがっているか”を表す数字です。求人倍率が高いときは景気が良く、低いときは景気が悪くなりやすい。
好状期に上昇し、不状期に低下する傾向があり、景気指数の「一致系列」に採用されています。
完全失業率との関係
- 有効求人倍率↑&失業率↓ → 景気が好調
- 有効求人倍率↓&失業率↑ → 景気が悪化
この2つをセットで見ると、雇用環境の“強さ”がわかります。
常用雇用指数(厚生労働省・毎月勤労統計調査)
企業が雇っている「常用雇用者(正社員+契約・パートなど継続雇用者)」の数の変化を指数化したものです。
基準年(今は2020年)=100として、「今どれだけ雇用が増減しているか」を見る指標。
常用雇用指数=月末の常用労働者数÷基準年の平均の常用労働者数×100
たとえば、
- 常用雇用指数=105 → 雇用が5%増加
- 常用雇用指数=98 → 雇用が2%減少
何を読み取るか?
企業が「人を増やす」=今後の仕事量に自信がある、というサイン。逆に、人を減らす=業績の先行きに慎重、というサイン。
→つまり、企業の景気の“見通し感”が反映されるデータなんです。
多くの企業において雇用者の解雇は最終手段として実施されることが多く、景気の動きが指数に反映されるのが遅いことから「遅行系列」に採用されています。
まとめると
| 指標 | 公開主体 | 意味 | 景気との関係 |
|---|---|---|---|
| 完全失業率 | 総務省 | 仕事を探しているが就職できない人の割合 | 下がるほど景気が良い(遅行) |
| 有効求人倍率 | 厚生労働省 | 求人数 ÷ 求職者数 | 上がるほど景気が良い(一致) |
| 常用雇用指数 | 厚生労働省 | 継続雇用者の増減を表す指数 | 上がると雇用環境が安定(遅行) |
⑫ 住宅関連統計
代表指標: 新設住宅着工戸数、住宅・土地統計調査、マンション市場動向調査など。
公表:国土交通省、総務省、不動産経済研究所
ポイント:
- 住宅投資は金利動向や所得環境に左右されやすい。
- 消費や建設関連業への波及効果も大きい。
住宅着工戸数(国土交通省)
新しく建て始めた住宅の数を毎月まとめたデータ。「家を建てよう」「マンションを作ろう」と着工(工事をスタート)した件数のこと。
これが増えているときは、「景気が良くて住宅ローンを組む人が増えている」「不動産投資が活発」など、経済が前向きに動いているサインになります。逆に減っていると、景気が慎重モードということも。
このうち新設住宅着工床面積は景気の動きに先行しているとして、景気動向指数の「先行系列」に採用されています。
住宅・土地統計調査(総務省)
これは5年に1回行われる住宅アンケート。全国の家庭に「家の種類」「築年数」「広さ」「家賃」「空き家の数」などを聞いています。
ポイントは「日本の住まいの現状をまるごと把握できる」こと。
たとえば、
- 空き家が増えている地域
- 賃貸より持ち家が多い地域
などを分析して、住宅政策(補助金や都市計画)にも使われます。
マンション市場動向調査(不動産経済研究所 など)
新築マンションの「販売数」「価格」「契約率」などを毎月まとめた調査です。
これを見ると、
- 新築マンションが売れているか
- 価格が上がっているか下がっているか
がわかります。
マンションは高額商品なので、売れ行きが良い=消費意欲が高い、という景気の目安にもなります。
とくに都市部では、このデータが景気の「先行指数」としてよく注目されます。
まとめると
つまりこの3つはそれぞれ、
- 住宅着工戸数 → 「建て始めた数」で“動き出し”をチェック
- 住宅・土地統計調査 → 「どんな家に住んでるか」で“現状”をチェック
- マンション市場動向調査 → 「売れ行き・価格」で“勢い”をチェック
というように、住宅市場を立体的に見るデータたちです。
⑬ 物価関連統計
代表指標: 消費者物価指数(CPI)、企業物価指数(PPI)。
公表: 総務省、日本銀行
ポイント:
- CPIは家計の物価実感に近く、金融政策判断の軸。
- 物価上昇率が日銀目標(2%)に達するかが焦点。
消費者物価指数(CPI:Consumer Price Index)
「私たちが買うモノやサービスの値段が、どのくらい変わったか」を数字で示したものです。総務省が毎月まとめています。
対象になるのは、スーパーの食料品、光熱費、家賃、交通費、外食、洋服、保育料…など、生活に身近なモノやサービス。
基準年と比較してどれくらい値上がり(または値下がり)したか」を計算しています。
たとえば:
- 去年よりCPIが+3% → 物の値段が平均して3%上がった
- CPIが-0.5% → ちょっとデフレ傾向
つまりCPIは、家計のリアルな「体感インフレ」をあらわす指標です。
日本銀行は2013年に物価安定の目標を前年比上昇率+2%と定めており、金融政策の目標値として用いられることも多いです。
企業物価指数(PPI:Producer Price Index)
日本銀行が出しているもので、「企業同士でやりとりする商品の価格変化」をあらわします。
たとえば、鉄鋼・木材・原油・半導体・小麦などの「原材料や中間製品」の価格。スーパーに並ぶ“最終価格”ではなく、メーカーや卸売業者が取引する段階の値段です。
たとえば:
- 原油や小麦の値段が上がる → 企業物価指数も上がる
→ 数か月後に、ガソリンやパンの価格が上がる(=消費者物価に波及)
なのでPPIは、「これからのCPIの動きを予想するための先行指標」とも言われます。
まとめると
- 企業物価指数(PPI):企業が「仕入れる」段階の物価
- 消費者物価指数(CPI):私たちが「買う」段階の物価
PPIが上がる → 企業のコストが増える → それを価格に転嫁するとCPIも上がる。
こうしてインフレが波及していくわけです。
ちょっと生活に引きつけると…
ニュースで「企業物価が前年比+8%!」とか聞いたら、「うわ、しばらくしたらスーパーの値段も上がりそうだな」と読めるようになります。
逆に企業物価が落ち着いてくると、「物価高、ようやく一段落かも」と感じられるわけです。
インフレーション(物価上昇)の3つのタイプ
インフレ=モノやサービスの値段が全体的に上がること。
でも「なんで上がるのか」でタイプが違うんです。
① ディマンド・プル・インフレ(需要に引っ張られるインフレ)
「みんながたくさん買うから、値段が上がる」タイプ。
景気が良くて、給料も上がって、モノがよく売れると、企業は値上げしても売れる。需要(買いたい人)が供給(作る量)を上回るので、物価が“引っ張り上げられる”んです。
例:人気ゲーム機やライブチケットが、みんな欲しくて価格が高騰する。
② コスト・プッシュ・インフレ(コストで押し上げられるインフレ)
「作るコストが上がって、仕方なく値上げする」タイプ。
原材料(原油・小麦など)や人件費、輸送費が上がると、企業は利益を守るために販売価格を上げます。
例:原油価格の上昇 → ガソリン代・物流コストアップ → スーパーの食品も値上げ。つまり、作る側のコストが物価を押し上げる。
③ ボトルネック・インフレ(供給の詰まりで起きるインフレ)
「必要なモノが足りない・作れないから値段が上がる」タイプ。
災害・戦争・サプライチェーンの混乱など、特定のモノが手に入りにくくなると、そこが“ボトルネック(首の細い瓶の部分)”になって全体の価格が上昇します。
例:半導体不足 → 車や家電の生産が減る → 買いたい人が多くて値上がり。
まとめると
| 種類 | 原因 | よくある場面 |
|---|---|---|
| ディマンド・プル | 買う人が多すぎ | 景気好調・給料アップ時 |
| コスト・プッシュ | 原価が上がる | 原油・円安・人件費上昇 |
| ボトルネック | 供給が詰まる | 戦争・災害・物流混乱 |
物価を測るときの“指数の数え方”の違い
インフレを数字で測るときには、基準をどうとるかが大事。
その代表が ラスパイレス指数 と パーシェ指数 です。
① ラスパイレス指数(Laspeyres)
「基準年の買い物カゴ」を基準に、今の価格を比べる。つまり、「昔と同じものを今買ったらいくらかかる?」を計算。
速報性が高くて、コストも安い。
なぜなら、「昔(基準年)のデータ」はもう手元にあるから。あとは“今の価格”だけ集めれば計算できる。つまり、データがすぐそろうし、調査も簡単。
たとえば「2020年に買ったモノのリスト」で、2025年の値段を調べるだけ。
→ 買う量は変わらない前提だから、サッと計算できる。
だから、速報性が高くて運用コストが低いんです。
CPI(消費者物価指数)はこれの算出方式を採用しています。
② パーシェ指数(Paasche)
「今の買い物カゴ」で、昔と今の価格を比べる。つまり、「今の生活スタイルで、もし昔の値段だったらいくらだったか?」を計算。
速報性が低くて、コストが高い
なぜかというと、「今の数量(買う量)」を正確に知るのが大変。「今どのくらいパン買ってる?米は?スマホは?」なんて、最新の購買データを集めるには時間がかかる。
しかも、比較年の数量を毎回集め直すから、計算が複雑で手間もコストもかかる。
たとえば「2025年の今、何をどれくらい買っているか」を全部調査して、その“今の買い物リスト”を使って、過去の価格で再計算する。
→ データ揃うのが遅れる(速報性が落ちる)。
じゃあ、なぜパーシェ式を使うの?
実はパーシェ指数は、“実際の行動”を反映できるのが強み。
人は値上げされたモノを買わなくなったり、安いモノに切り替えたりしますよね。この代替効果を反映できるのがパーシェ式。だから、現実の経済活動をより正確に反映します。
GDPデフレーター(経済全体の物価)では、正確さを重視するためパーシェ式が採用されています。
まとめると
| 指数 | 基準にする数量 | 速報性 | コスト | 特徴 | 採用例 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラスパイレス指数 | 基準年の数量 | 高い(早い) | 安い | 過去の買い方で比べる。やや高めに出る | 消費者物価指数(CPI) |
| パーシェ指数 | 現在の数量 | 低い(遅い) | 高い | 現実の買い方を反映。やや低めに出る | GDPデフレーター |
パーシェはデータ集めが重い、ラスパイレスはスピード勝負 なイメージ。
⑭ マネー関連統計
代表指標: マネーストック、マネタリーベースなど。
公表: 日本銀行
ポイント:
- マネーストック=民間の資金量、マネタリーベース=日銀が供給する資金量。
- 金融緩和や引き締めの状況を示す。
マネーストック(Money Stock)
マネーストックとは、家庭や企業が実際に持っているお金の総量のことです。つまり、世の中を流れている“使えるお金”の量を表しています。
銀行に預けられている預金や、みんなが持っている現金などが含まれます。経済の動きを見る上で重要な指標で、お金の巡り具合=経済の血流を知ることができます。
日銀は、このマネーストックを「どこまでお金とみなすか」でいくつかの分類に分けています。
- M1:現金+当座預金など、すぐ使えるお金
- M2:M1+定期預金(日本では主にこれを使って分析)
- M3:M2+信用金庫などを含む、より広い範囲のお金
金融機関や中央政府が保有する通過量は含まれません。
マネーストックが増えると、企業や個人が使えるお金が増え、景気が活発になります。逆に減ると、お金の流れが滞り、景気の減速につながります。
マネタリーベース(Monetary Base)
マネタリーベースとは、日銀が金融機関に供給しているお金の総量のことです。
別名「ハイパワード・マネー(強力なお金)」とも呼ばれます。
中身は次の2つです。
- 市中に出回っている現金(銀行券+硬貨)
- 銀行が日銀に預けている当座預金
マネタリーベースは、いわばお金の“タネ”です。日銀がこのタネを銀行に供給し、銀行がそれをもとに貸し出しを行い、最終的に企業や個人が使うお金(=マネーストック)が増えていきます。
関係性のイメージ
日銀 → 銀行へお金を供給(マネタリーベース)
↓
銀行 → 企業・個人に融資・預金を通じてお金を流す
↓
企業・個人が実際に使うお金(マネーストック)
まとめると
| 指標 | 意味 | 誰のお金か | 主な内容 | 発表元 |
|---|---|---|---|---|
| マネタリーベース | 日銀が供給する“お金のタネ” | 日銀・銀行 | 現金+日銀当座預金 | 日本銀行 |
| マネーストック | 世の中を流れる“使えるお金” | 家計・企業 | 現金+預金 | 日本銀行 |
つまり、
- マネタリーベース=日銀が経済に送り出す「お金の元」
- マネーストック=そのお金が世の中を回る「結果」
この2つの動きを見ることで、「お金の流れ」と「景気の勢い」を読み取ることができます。
⑮ 国際収支統計
意味: 日本と海外の取引(モノ・サービス・投資など)の収支。
公表: 財務省と日銀の共同(毎月)
ポイント:
- 経常収支が黒字=海外からの所得が多い。
- 貿易収支・所得収支・サービス収支などに分かれる。
まとめ:経済指標は単独ではなく「組み合わせ」で読む
経済指標は単独ではなく「組み合わせ」で読むことが大切です。
たとえば、鉱工業指数が上昇+稼働率が高い+雇用が改善なら景気拡大局面。逆に、在庫が増加+機械受注が減少していれば調整局面に入る可能性も。
経済の全体像を示す指標
| 指標名 | 概要 | 公表機関 | チェックポイント |
|---|---|---|---|
| GDP(国内総生産) | 国内で生み出された付加価値の合計。経済の“サイズ”。 | 内閣府 | 実質GDP成長率に注目。前期比・年率換算で景気判断。 |
| 景気動向指数(CI) | 景気の現状・方向性を表す複合指数。 | 内閣府 | 「先行」「一致」「遅行」3種類。100超=好調。 |
| 日銀短観 | 企業の業況判断調査。景況感の定点観測。 | 日本銀行 | 大企業製造業DIが代表値。プラス=景況感良好。 |
企業活動を示す指標
| 指標名 | 内容 | 公表機関 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 機械受注統計 | 企業の設備投資意欲の先行指標。 | 内閣府 | 「民需(船舶・電力除く)」が注目対象。 |
| 鉱工業指数 | 製造業などの生産動向を示す。 | 経産省 | 生産・出荷・在庫の3系列。GDPと連動。 |
| 稼働率指数 | 設備がどれだけ動いているか。 | 経産省 | 高いほど需要旺盛。景気減速時に低下。 |
| 在庫循環 | 生産と在庫の関係から景気局面を分析。 | 経産省 | 「積み増し→調整→減少→再積み増し」で循環。 |
| 設備投資比率 | 利益に対してどれだけ投資しているか。 | 各種調査 | 攻めの経営姿勢を示す。 |
家計・生活を示す指標
| 分野 | 主な統計 | 公表機関 | チェックポイント |
|---|---|---|---|
| 家計・消費関連 | 家計調査、消費動向指数、小売販売額 | 総務省、経産省 | 実質消費支出で消費の強さを確認。 |
| 雇用関連 | 有効求人倍率、完全失業率 | 厚労省、総務省 | 1以上=求人過多。雇用改善は景気後追い。 |
| 住宅関連 | 新設住宅着工戸数 | 国交省 | 住宅投資は金利に敏感。建設業に波及。 |
物価・金融・国際動向を示す指標
| 分野 | 主な統計 | 公表機関 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|
| 物価関連 | 消費者物価指数(CPI)、企業物価指数(PPI) | 総務省、日銀 | CPIが日銀目標2%に届くか注目。 |
| マネー関連 | マネーストック、マネタリーベース、金利 | 日銀 | 金融緩和・引き締めの方向を示す。 |
| 国際収支統計 | 経常収支、貿易収支、所得収支 | 財務省、日銀 | 黒字=海外からの所得超過。円相場にも影響。 |

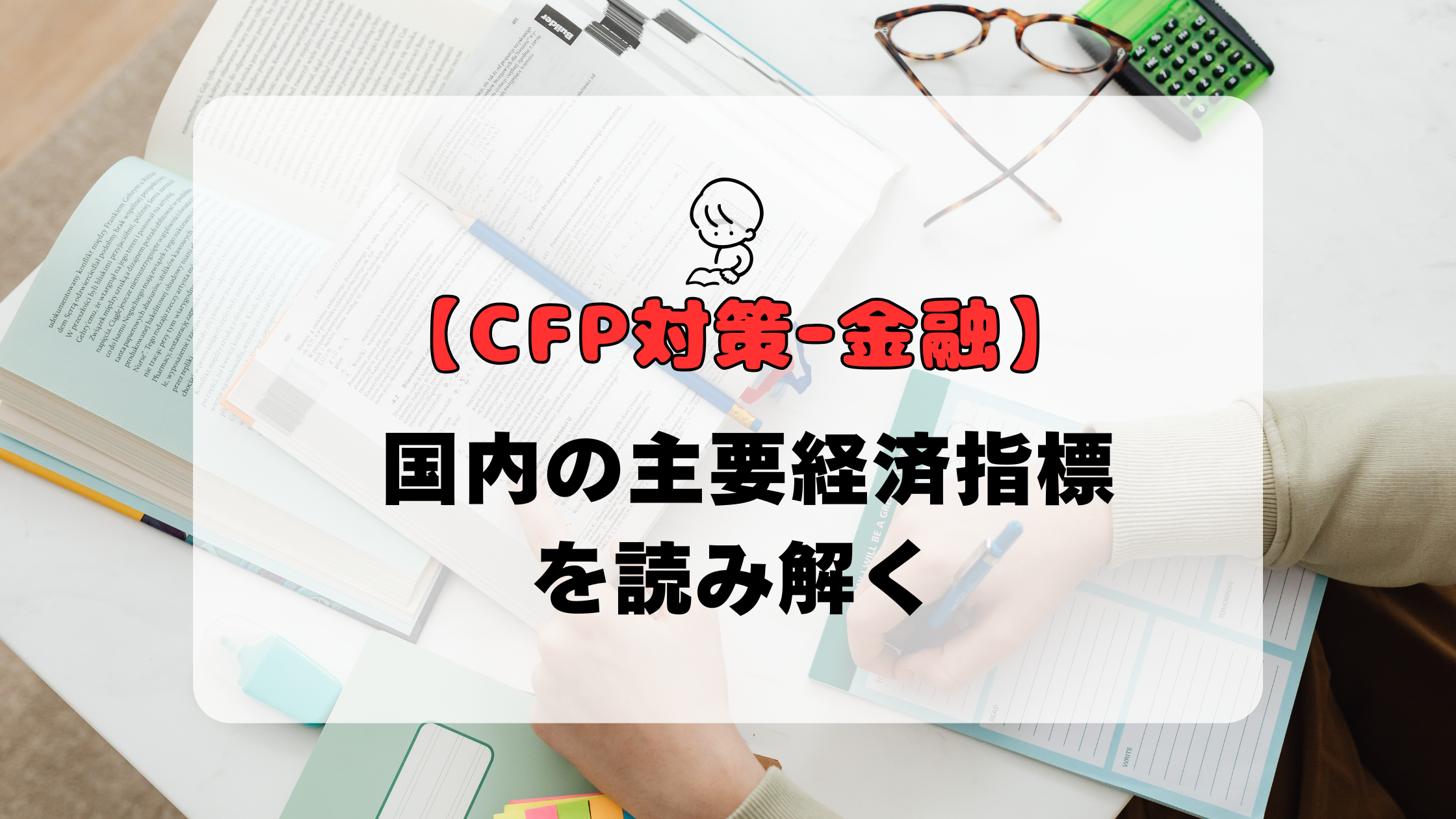
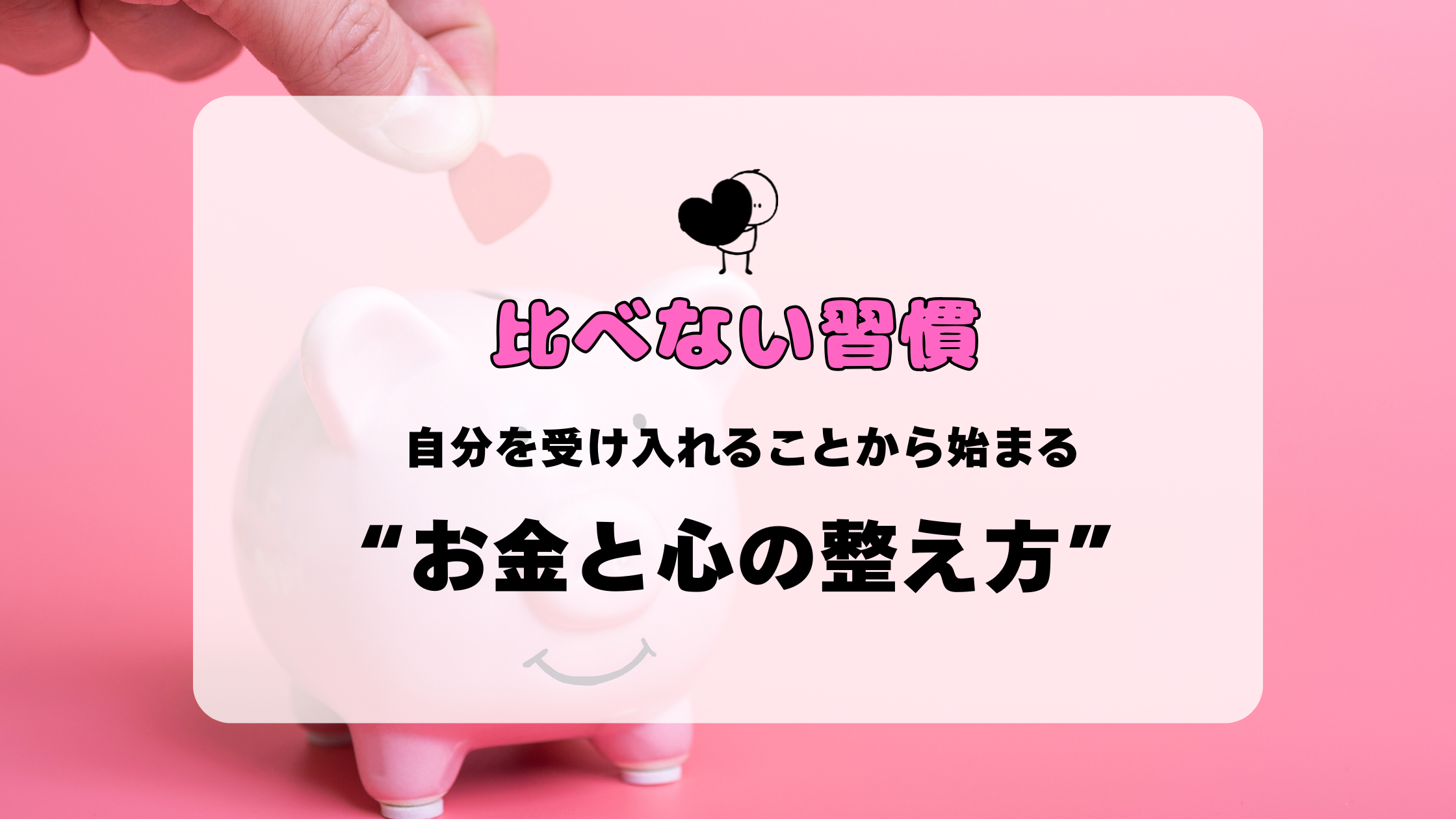
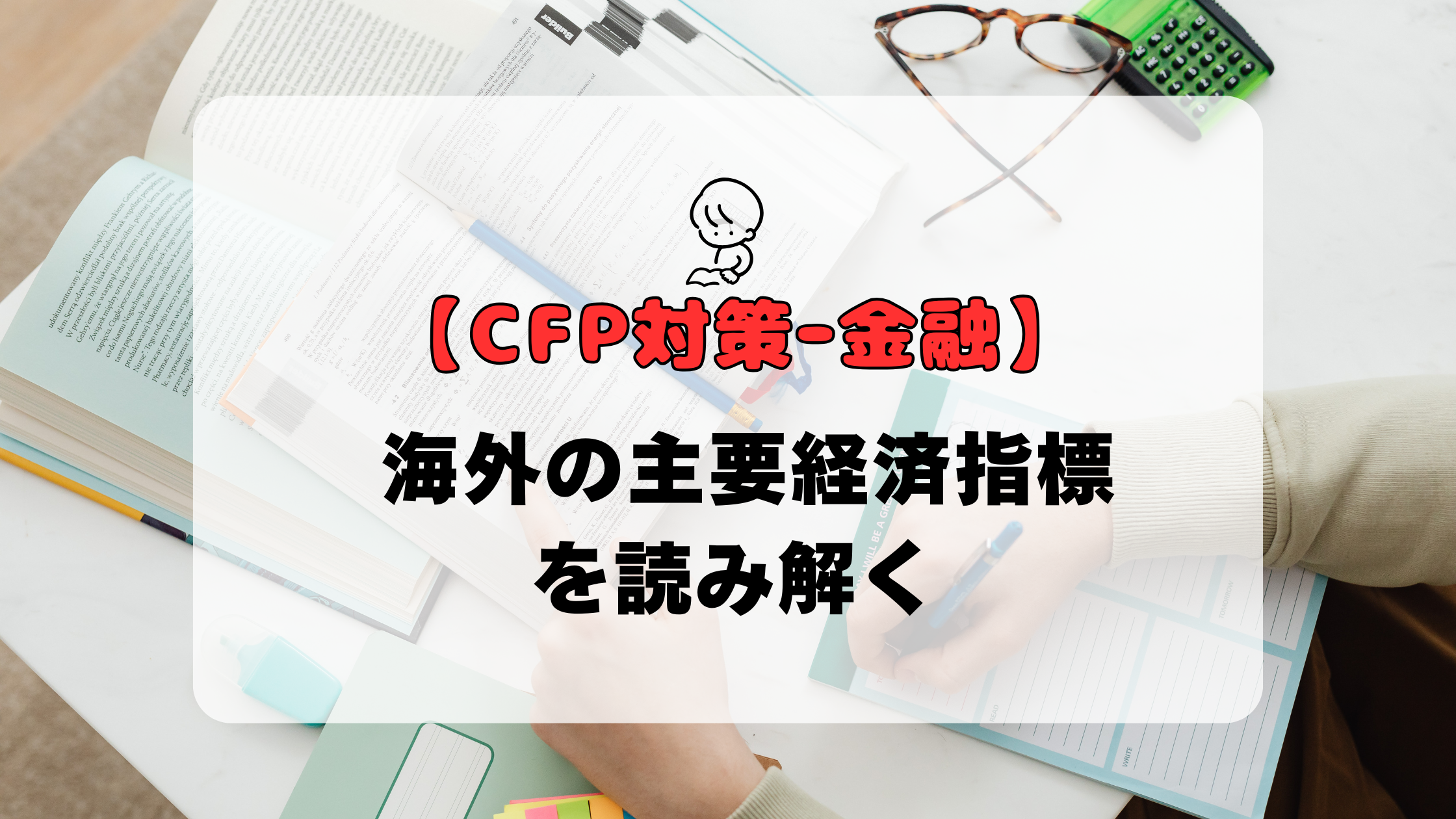
コメント