「もし自分に何かあったら、家族はどうなるんだろう?」
そう考えたとき、まず気になるのが遺族年金。でも「若いと支給されない」「子どもがいないとダメ」など条件がいくつかあり、わかりづらいですよね。
また、最近はフルタイムワーママも多いのに、だいたいの説明が“夫が死亡したケース”で書かれていて、じゃあ働く妻(わたし)が亡くなった場合はいくら支給されるんですか!と言いたくなります。
今回は妻が亡くなるケースも踏まえて遺族年金について基礎知識をまとめてみました。
「遺族年金」とは?
家族の中で働いていた人が亡くなったとき、残された家族の生活を支えるために支給される公的な年金制度です。大きく分けると次の2つがあります。
- 遺族基礎年金(国民年金加入者向け)
- 遺族厚生年金(厚生年金加入者向け)
つまり、国民年金と厚生年金に加入している会社員は、一定条件を満たせば遺族基礎年金+遺族厚生年金を受給できる可能性があります。
遺族基礎年金とは
対象
主に子のいる配偶者 or 子ども本人
支給額(2025年度)
国民年金の加入期間によらず一律で、子どもの人数に応じた金額が加算されます。
- 基本額:月約6万9,300円(年額83万1,700円)
- 子の加算:2子 各月約1万9,900円(年額23万9,300円/人)、第3子以降 各約6,650円(7万9,800円/人)
受給できる条件(以下条件をすべて満たす必要がある)
- 亡くなった人が国民年金に加入していた(または老齢基礎年金を受け取る資格があった)
- 子どもが18歳になった年度の末日まで(または障害1・2級なら20歳未満)
受給できる人
- 子どものいる配偶者(男女問わず)
- または、子ども本人(両親がいない場合)
つまり「子どもがいること」が条件です。子どもがいない場合は、遺族基礎年金は支給されません。
遺族厚生年金とは
対象
厚生年金に加入していた人が亡くなった場合(会社員や公務員など)
支給額の目安
亡くなった方の報酬比例部分※の年金 × 4分の3
※1:平成15年4月以降:平均標準報酬額×5.481÷1,000×加入月数※2
※2:報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
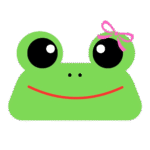
※1:報酬比率部分はねんきん定期便の
3.これまでの加入実績に応じた年金額 (2)老齢厚生年金
に該当します。
※2:22歳から厚生年金に加入している人はおおむね47歳前後までは300月計算でOKです。
例:月収35万円・加入期間10年(120月)の場合
通常なら
35万円 × 5.481/1000 × 120 × ¾ = 約172,000円/年(=月約14,000円)
ですが、「みなし300月」で計算すると
35万円 × 5.481/1000 × 300 × ¾ = 約431,000円/年(=月約36,000円)
➡ 若くして亡くなった場合でも、遺族厚生年金は月約3.6万円ほど もらえる。
受給できる人の条件(男女で違いあり)
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 妻が受け取る場合 | 子がいなくても夫が厚生年金加入中に亡くなれば、妻は受給対象。年齢制限なし(ただし30歳未満で子なしは5年で打ち切り)。 |
| 夫が受け取る場合 | 子がいない場合は原則受給できません。子がいる場合のみ支給対象になります。 |
つまり、「妻が夫を亡くした場合」は比較的手厚く、「夫が妻を亡くした場合」は、子がいないと支給されないという違いがあります。
我が家のケースで考えてみる
👨夫30代後半
👩妻30代前半(わたし)
👦息子4歳
👶娘0歳
夫が亡くなった場合
→ 妻(わたし)と子どもが支給対象。
- 遺族基礎年金
妻+子ども(2人)で、約6万9,300円+(1.9万×1人)=月約9万円
→ 年間約108万円支給。 - 遺族厚生年金
夫の収入に応じて上乗せ。
合計:月12~13万円前後が支給される可能性あり。
妻(わたし)が亡くなった場合
→ 夫が受け取れるのは、子どもがいる間のみ。
- 遺族基礎年金
夫+子ども(2人)で、約9万円/月(同上)→ 子どもが18歳の年度末まで。 - 遺族厚生年金
妻(わたし)が厚生年金加入中であれば、夫も子どもがいる間は受給可能。
合計:月12~13万円前後が支給される可能性あり。
子どもが独立すると支給は終了します。子どもが小さいうちは支えになりますが、長期的には備えが必要。
男女での違いまとめ
| 比較項目 | 妻が亡くなった場合(夫が受給) | 夫が亡くなった場合(妻が受給) |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子がいる場合のみ受給可 | 子がいる場合のみ受給可 |
| 遺族厚生年金 | 子がいないと原則不可 | 子がいなくても可(条件あり) |
| 支給期間 | 子が18歳になるまで | 子が18歳になるまで+妻の終身 or 再婚まで |
我が家に必要な備えを考えてみる
我が家のようにまだ子どもが小さい場合、遺族年金だけで月12万円前後の支給が見込めても、家賃・教育費・生活費を考えると足りないケースもあります。
特に子どもの進学や親の働き方の変化も見据えて、死亡保険で想定される不足分を補えるようにしておくと安心です。
まとめ:遺族年金を前提に、足りない分を民間保険でカバー
遺族年金は、国が用意してくれている「最低限の生活を守る制度」です。それを踏まえて、教育費や住宅費など、家族それぞれのライフスタイルに合わせた備えが必要です。
- 公的保障(遺族年金)でまかなえる範囲を知る
- 家計に足りない分を民間保険で補う
- 万が一のときにも「生活を続けられる設計」にしておく
家族を守るのは「愛情」と「知識の積み重ね」。今のうちから少しずつ整えていきましょう。

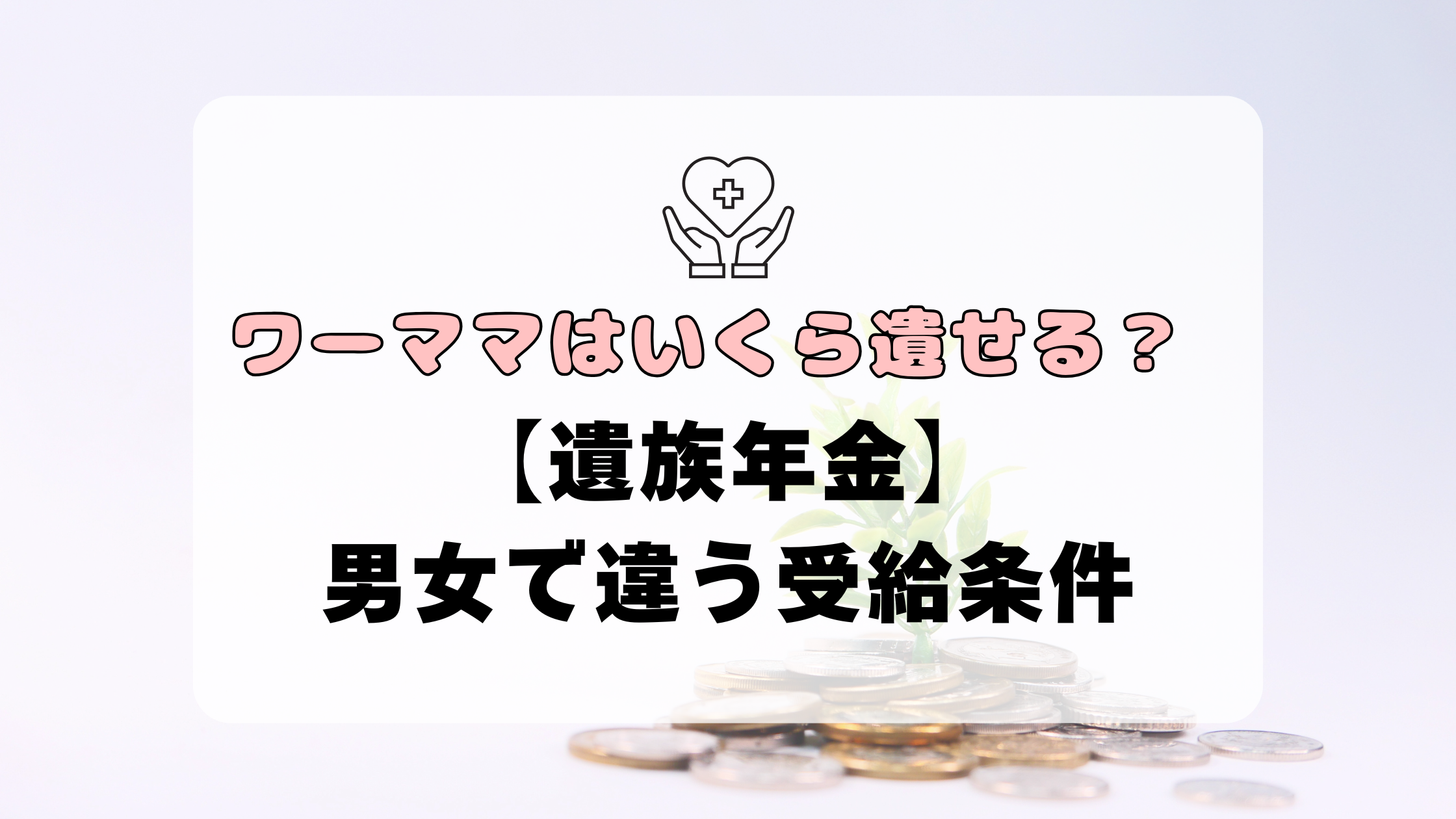
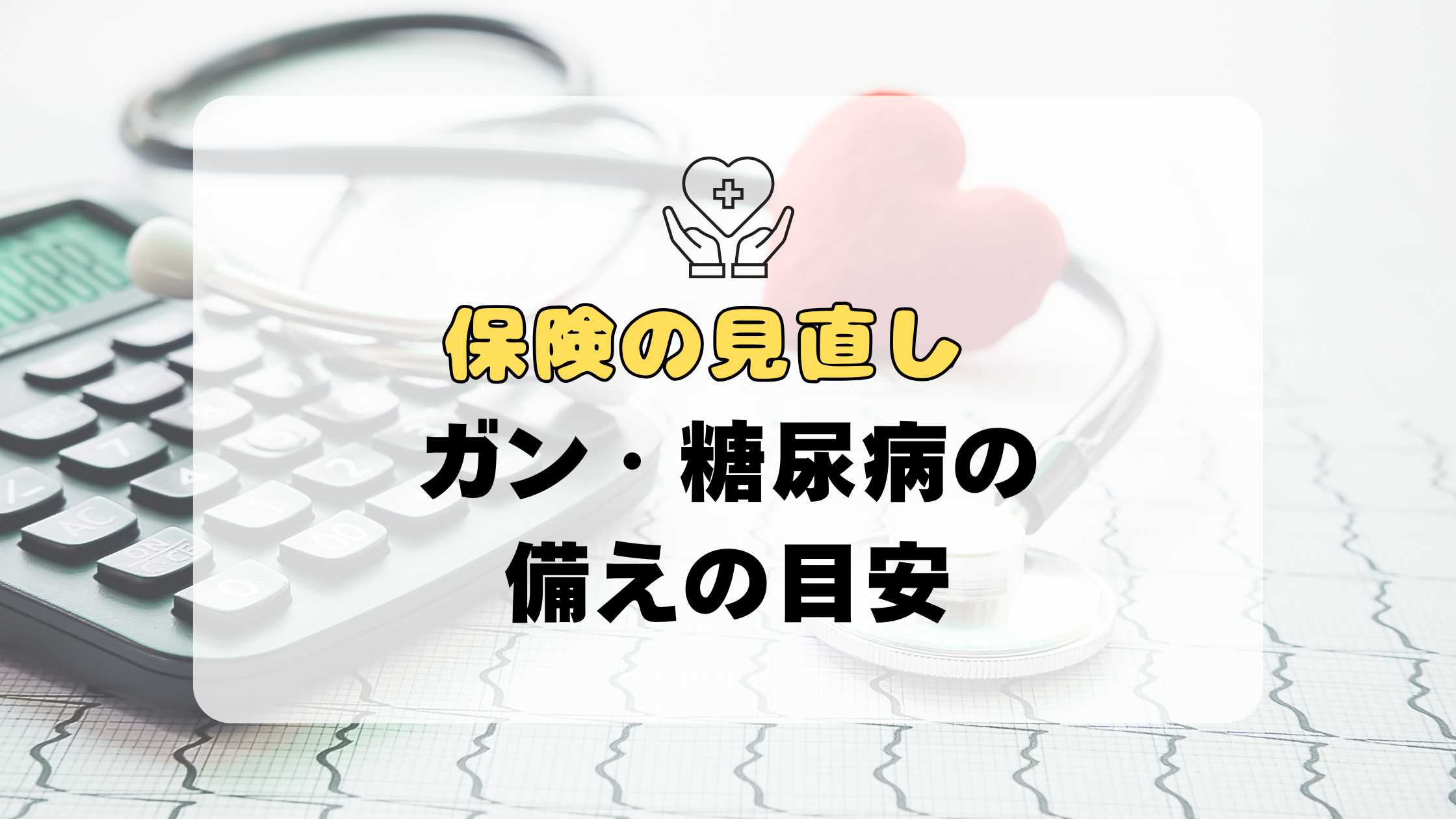
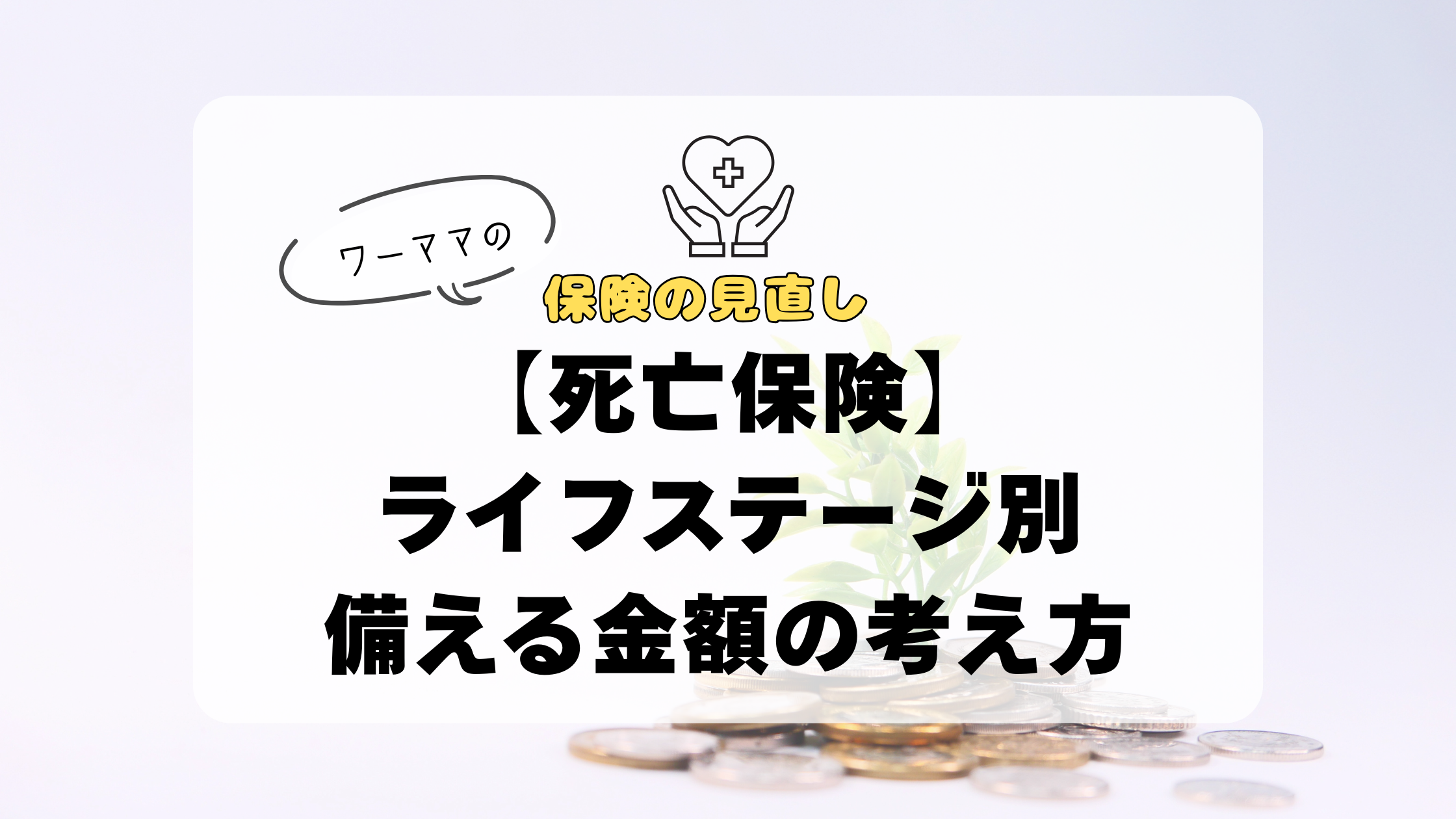
コメント