「もし自分に何かあったら…」
子どもが小さいうちは、そんな不安が頭をよぎることもありますよね。
でも、すべてを保険でカバーしようとすると保険料も高くなってしまいます。一方で、運用を組み合わせることで「必要な時期に必要な分だけ」備えることも可能です。
今回は、子どもが2人いる母親がどれくらいの死亡保障を考えるべきか、子どもの成長段階に合わせて整理してみます。
死亡保険金の一般的な考え方
死亡保険は「いざというとき、残された家族が困らないようにするお金」です。
目的別に分けると、主に次の3つで構成されます。
| 目的 | 内容 | おおよその目安 |
|---|---|---|
| 葬儀費用 | 葬儀・お墓・お布施など | 約100〜200万円 |
| 生活費 | 配偶者と子どもが生活を続けるための費用 | 月10〜20万円 × 必要年数 |
| 教育費 | 子どもの進学・学費など | 1人あたり約1,000万円(大学まで) |
つまり、「葬儀費+生活費+教育費」から遺族年金や貯蓄を差し引いた金額が、自分にとって“ちょうどいい保障額”になります。
たとえば
子ども2人(大学まで)+毎月15万円の生活費を10年間カバー+葬儀費150万円
→ 約3,000万円が一つの目安です。
ただし、遺族年金や運用資産がある場合はここから減額してOKです。
考え方のポイント
- 「必要保障額」は年齢・子どもの成長とともに減る
→ 大学資金などの「大きな支出時期」を過ぎれば、生活保障額は小さくてOK。 - 「運用資産」と「保険金」を組み合わせる
→ NISAで積み立てた老後資金等の資産を“将来の教育資金の一部”として活用する。 - 死亡時に「遺族年金+保険金+運用資産」で生活を支える
→ 国の保障(遺族年金)をしっかり踏まえた上で、過不足を自助でカバーする。
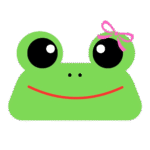
すべてを保険でカバーするのもひとつの案ですが、資産運用も併用して考えると柔軟性のある資産を増やすことができるので合理的です。
国の制度「遺族年金」でどれくらいカバーできる?
まずは国のベース保障から。
たとえば子がいる会社員の妻が亡くなった場合、自身(夫)の前年の収入が850万円未満(所得が655万5000円未満)であれば子が18歳に到達するまで夫は妻の遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取ることができます。夫と子どもが受け取れる年金は以下のとおり。
- 遺族基礎年金(共通):年間約83万円+子の加算24万円(2人目。3人目以降は約8万円)
- 遺族厚生年金(会社員):報酬により異なるが平均標準報酬額35万円/月で年間約43万円ほど
合計すると、年間150〜250万円ほどの保障になります。
会社員でない場合、遺族基礎年金分のみの支給になります。
子が居ない夫婦の場合、夫は55歳以上でなければ妻の遺族厚生年金を受給することができません。遺族基礎年金も子が居ないため受給できません。
妻は子が居なくても夫の遺族厚生年金を受給することができます。しかし30歳未満で子がいない場合は5年間で終了します。遺族基礎年金は夫同様、子が居ないため受給できません。
子どもの成長段階別「必要保障額」の考え方
子がいる場合に確保したいのは子供の教育資金。子供の年齢期において大学までを見据えた必要保証額を整理してみます。
| 子どもの年齢期 | 状況 | 必要保障額の目安 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 保育園・幼稚園期 | 教育費がこれからかかる。生活費の比重大。 | 約2,000〜2,500万円 | 大学資金も含めて最大の保障額。 |
| 小学生期 | 教育費が増え、NISA資産も増加。 | 約1,500〜2,000万円 | 保険を少し減らし始めるタイミング。 |
| 中高生期 | 教育費ピーク。NISAで600〜900万円程度貯まる頃。 | 約1,000万円 | 保険より運用を中心にカバー。 |
| 大学生期 | NISA資産を取り崩して教育費に。 | 約500〜1,000万円 | 保険金は少額でOK。生活費補填中心。 |
NISAでの運用を組み合わせる案
たとえば、年間50万円を利回り3%で積み立てた場合の目安は以下の通りです。
| 積立年数 | 積立総額 | 想定運用益 | 合計資産 |
|---|---|---|---|
| 10年 | 500万円 | 約85万円 | 約585万円 |
| 15年 | 750万円 | 約200万円 | 約950万円 |
| 18年 | 900万円 | 約290万円 | 約1,190万円 |
この運用では大学入学前後の時期に約1,000万円の資産形成が可能です。
例えば上記のように自身の老後資金を準備しているのであれば、死後に運用成果を「教育資金の一部」として使ってもらうことで、保険金を無理に多く設定しなくても安心なラインを確保できます。
年齢が上がるほど「保険金は減っていい」理由
子どもが成長するにつれて、
- 教育費のゴールが近づく
- 貯蓄・運用資産が増える
- 遺族年金を受け取れる期間が短くなる
…という変化が起こります。
そのため、最初に大きく保険をかけ、年齢とともに減額していく「逓減型」や「定期更新型」の保険も良いでしょう。
夫の収入とのバランスを考える
夫の収入も想定して保険金額を考えることも大切です。
子どもが小さいうちは父親がすぐに仕事を減らすことが難しかったり、逆に仕事をセーブして今まで通り働けなかったりすることが予想されます。「生活費+子育てサポート費」をまかなう備えがあると安心です。
ケース①:夫の収入で 1人分の大学資金は準備できる場合
- 残り1人分の大学資金+生活費補填を保険で備える。
- 必要保障額:約1,000〜1,500万円程度
- 運用資産で不足分をカバー。
無理に大きな保険に入らず、「生活をつなぐ」目的に絞るのが◎。
ケース②:夫の収入で 2人分の大学資金を準備できる場合
- 教育資金の備えはすでに十分。
- 生活費補填としての保険だけでOK。
- 必要保障額:約1,000万円以下でも十分。
保険料を抑えて、浮いた分を積み立て投資に回すのもおすすめ。
トータルでの目安:運用+保険で備えるバランス
| 目的 | 保険で備える | 運用で備える | 合計目安 |
|---|---|---|---|
| 教育資金 | 500〜1,000万円 | 約1,000万円 | 約1,500〜2,000万円 |
| 生活費 | 500〜1,000万円 | (一部NISA取り崩し) | 約1,000万円前後 |
| 合計 | 1,000〜2,000万円 | 運用で育てる | 家計に無理のない備え方 |
まとめ
- 死亡保険は「葬儀費+生活費+教育費」から逆算して考える
- 国の遺族年金や運用を組み合わせれば、過剰な保険は不要
- 子どもの成長に合わせて、家計の貯蓄を考慮した必要額を見直していくと良い
保険で守り、運用で育てる。
どちらも「家族の安心」をつくる手段です。焦らず、自分たちの家計とライフステージに合った“ちょうどいい備え”を見つけていきましょう。

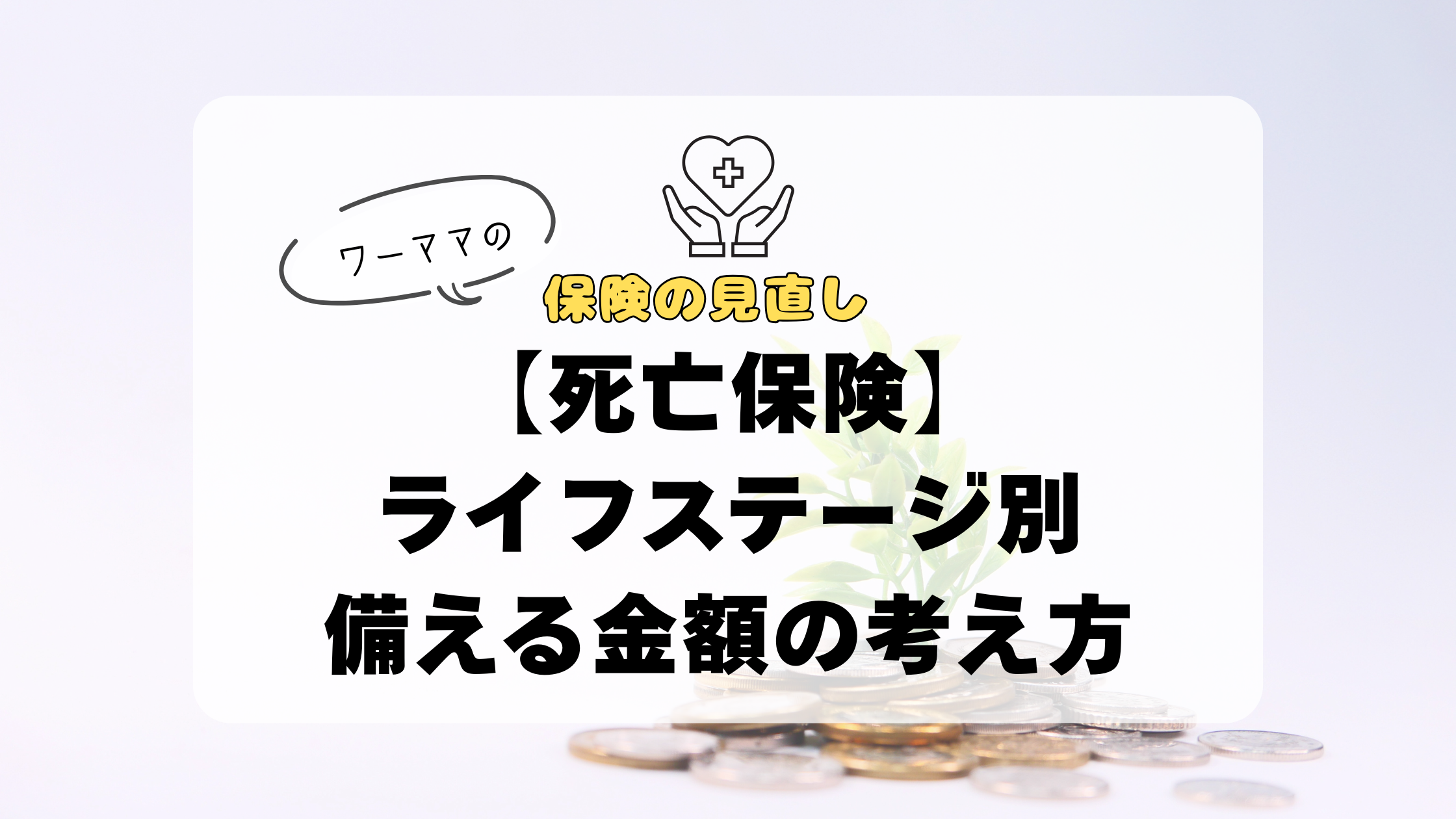
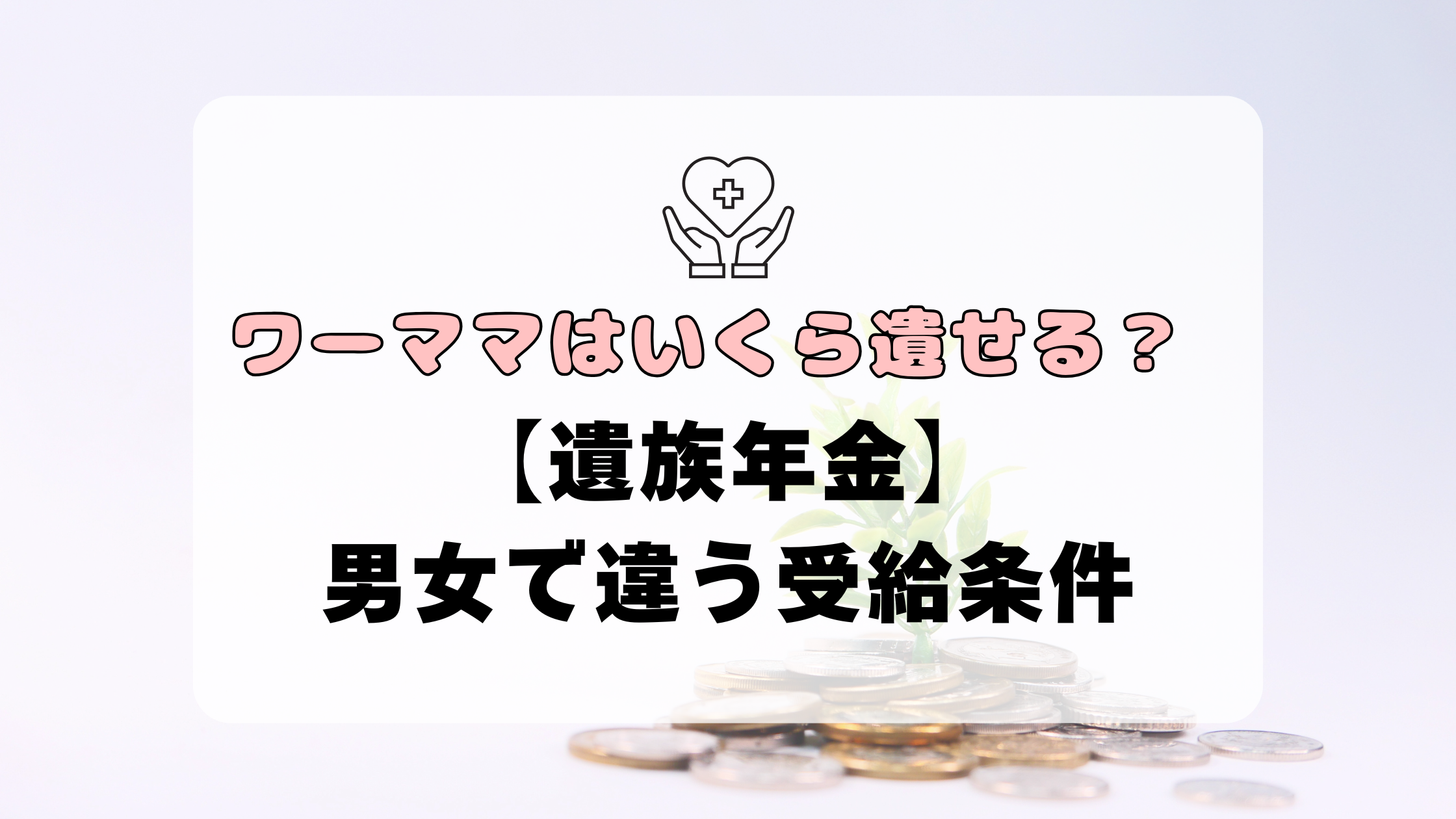
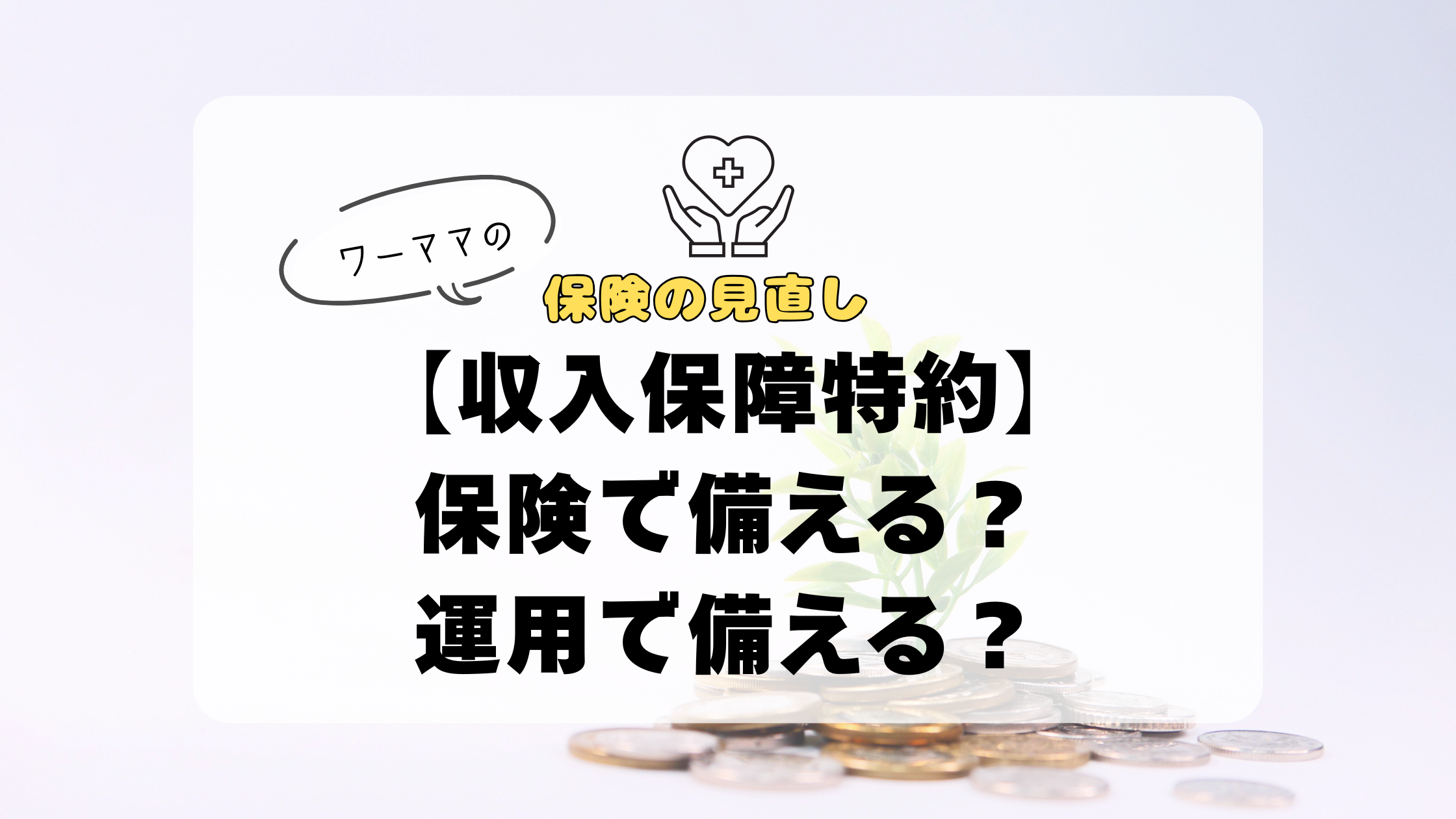
コメント