医療保険の見直しをしていると、「入院1日いくらの保障にすればいいんだろう?」「そもそも保険って必要?」という疑問が出てきます。
ここでは、実際の入院費を数字で見ながら、貯蓄と保険どちらが合理的かを会社員目線で考えていきます。
入院にかかる費用
厚生労働省の「医療給付実態調査(令和4年度)」によると、日本の平均的な入院費用は次の通りです(自己負担3割ベース)。
| 病気の種類 | 平均入院日数 | 自己負担の目安 |
|---|---|---|
| 一般的な病気 | 約16日 | 約20〜30万円 |
| 心疾患・脳疾患 | 約20〜30日 | 約25〜45万円 |
| がん | 約12〜20日 | 約15〜25万円 |
ここに差額ベッド代(個室1日5,000〜15,000円)や交通費、日用品費が加わります。
全体で1回の入院に30〜50万円程度が現実的な水準です。
高額療養費制度で「自己負担は月9万円ほど」まで軽減
多くの30〜40代の共働き世帯の場合、高額療養費制度により1か月の自己負担上限は約8〜9万円。
つまり、入院費が50万円かかっても、あとから40万円前後が払い戻される仕組みです。
一時的に必要なのは「立て替え資金+雑費」で、多くのケースでは10〜15万円程度の現金があれば足ります。
会社員の強い味方「傷病手当」「労災保険」
病気やケガで長く仕事を休むことになった場合、会社員には公的な補償制度が2種類あります。それが「傷病手当金(業務外)」と「労災保険(業務内・通勤中)」です。
両方とも“いざというときの収入の穴を埋める”仕組みですが、適用される場面が違います。
傷病手当金とは(業務外の病気・ケガ)
対象となる条件
- 仕事以外での病気やケガで、働けない状態になったとき
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休むこと
- 休業期間中に給与の支払いがない、または傷病手当金より少ない場合
- 健康保険の被保険者であること(勤務先で社会保険加入していればOK)
もらえる金額の目安
1日あたり「標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3」が支給されます。月収の約3分の2が日割りでもらえる制度です。
給付期間
4日目から1年6か月
※失業中に病気やケガで求職活動できないときに支給される「雇用保険の傷病手当」というものもあります。ただし、これは勤務中の病気ではなく、求職中に体調を崩して働けなくなった場合の制度です。
労災保険とは(業務中・通勤中の病気・ケガ)
対象となる条件
- 業務中、または通勤途中に発生したケガや病気であること
- そのケガ・病気によって働けない状態になったこと
- 会社を通して「労災申請」を行い、労働基準監督署に認定されること
もらえるお金の種類
- 療養補償給付:治療費はすべて労災保険が負担(=自己負担ゼロ)
- 休業補償給付:休業4日目以降、給料の約8割(正確には60%+特別支給金20%)が支給
給付期間
4日目から治癒まで(無期限)
傷病手当金と労災保険まとめ
これらの制度をまとめると以下のようになります。
| 制度 | 対象 | 医療費補填 | 休業補填の上限期間 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険(傷病手当金) | 業務外の病気・ケガ | 自己負担3割 | 最長1年6か月 | 私生活での病気・ケガをカバー |
| 労災保険(療養・休業補償) | 業務中・通勤中 | 全額無料 | 上限なし(治療が続く限り) | 補償が手厚く長期療養も安心 |
| 雇用保険(傷病手当) | 失業中の病気・ケガ | — | 最長3年 | 失業給付が一時停止される代わりに支給 |
年収450万円の人が16日入院した場合のシミュレーション
前提条件
- 年収:450万円(月収換算37.5万円)
- 日給換算:37.5万円 ÷ 30 = 12,500円
- 入院:16日間
- 入院期間中に土日が4日含まれると仮定(実働休業=12日間)
- 給付対象は「4日目以降」なので、実際の支給対象は8日間ほど
① 業務外の病気・ケガ(=傷病手当金)
計算式:12,500円 × 2/3 × 8日 = 約66,600円
※治療費は自己負担3割(高額療養費制度で上限あり)
② 業務中・通勤中のケガ・病気(=労災保険)
計算式:12,500円 × 0.8 × 8日 = 約80,000円
※治療費は全額無料(労災病院または指定医療機関での治療に限る)
結果をまとめると
| 区分 | 給付金額(16日入院・土日考慮) | 治療費負担 | 給付開始 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 傷病手当金(業務外) | 約6.6万円 | 自己負担3割(高額療養費で上限) | 4日目~ | 給与支給があれば調整あり |
| 労災保険(業務内) | 約8万円 | 全額無料(労災負担) | 4日目~ | 通勤中の事故も対象 |
わたしの加入中プランを検討
- 月額保険料:5,379円
- 入院一時金:1回50,000円
- 入院給付金:1日5,000円(終身)
女性特有の疾病・ガン・成人病が該当すればそれぞれ5,000円上乗せ - 手術給付金:1回50,000~200,000円(終身)
仮に年1回16日入院したとして、給付金は
手術なし:5,000円 × 16日 + 一時金50,000円 = 13万円。
手術あり:5,000円 × 16日 + 一時金50,000円 + 手術給付50,000円 = 18万円
これに対し、支払う保険料は年間 5,379円 × 12=64,548円。
手術のない入院であれば2年に1回入院するなら、手術ありの入院であれば3年に1回入院するならトントン、それ以上入院しなければ“払い損”という構図です。
こうみると、そこまで頻繁に入院するかな…?というのがわたしの正直な気持ちです。
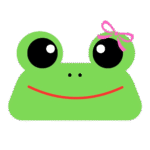
出産も給付の対象になったので、保険金を受け取りました。入院一時金+入院給付+女性疾患給付+手術給付(帝王切開)=総額25万円の給付になりました。出産もこれまでと思っているので辞め時かなあ。
もし保険料を貯金・運用したらどうなる?
月5,379円を80歳まで積立・運用すると仮定して比較してみましょう。
(30歳から50年間、年利5%・複利運用)
- 月額5,379円 × 12か月 × 50年 = 元本 322万円
- 年利5%で複利運用 → 約 1,290万円 に成長!
つまり、同じお金を積み立てて運用すれば、一生分の入院費(仮に10回分=500万円)をまかなってもお釣りがくるレベルです。
どの程度の現金を備えるべきか
16日ほどの入院なら、傷病手当金や労災保険で6〜8万円前後の収入補填が見込めます。
加えて、高額療養費制度を組み合わせれば、家計へのダメージはかなり抑えられます。
とはいえ、最初の数日間(待期期間)や差額ベッド代・交通費などは手出しになるので、最低でも10〜15万円程度の現金はいつでも使えるようにしておくと安心です。
それ以上の額や3日以内の入院・手術、補填に備えたいのであれば保険の加入を検討すると良いかもしれませんね。
どちらがいい?保険 vs 貯蓄
| 観点 | 保険で備える | 貯蓄・運用で備える |
|---|---|---|
| メリット | 突発的な入院でもすぐ給付金が出る。心理的安心感がある。 | 貯めたお金は使途自由。長期で見れば資産が増える。 |
| デメリット | 使わなければ損。支払いが長期にわたり資産形成を圧迫。 | 突発的な出費に即対応できない場合がある。 |
| 向いている人 | 貯金が苦手/片方が入院すると家計が厳しい人 | 貯金・積立が習慣化できている人/資産運用をしている人 |
結論:安心感か、効率か
もし「数十万円の貯金がある」「家計のキャッシュフローに余裕がある」なら、入院保険を小さくして、その分を積立・投資に回す方が合理的です。
逆に、「貯金が少ない」「どちらかが倒れると家計が止まる」なら、今のような入院特約を“安心の定期預金”と割り切って持っておくのもアリ。
まとめ:入院保険は「お守り」レベルで十分
- 平均入院費は30〜50万円
- 高額療養費制度で実際の自己負担は10〜15万円程度
- 1日5,000円の保障で多くのケースに対応可能
- 月5,000円台の保険料なら、運用に回す方がリターン大
- ただし、貯金が少ない場合は「お守り代」として加入もOK
人生100年時代、保険で安心を“買う”か、貯蓄で安心を“作る”か。
どちらを選んでもいいけれど、数字で見比べて納得したうえで選ぶことが、一番の安心につながります。

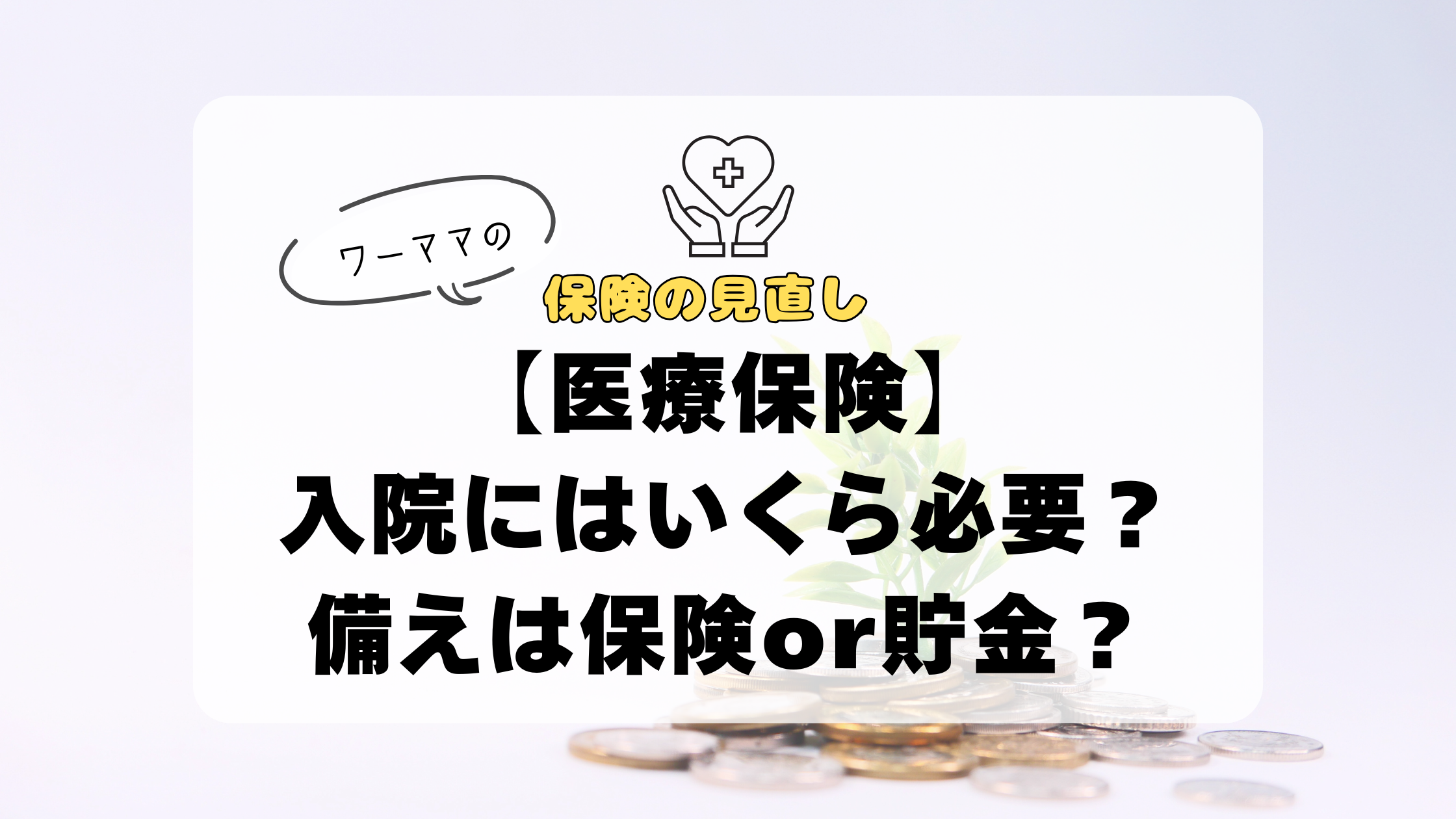
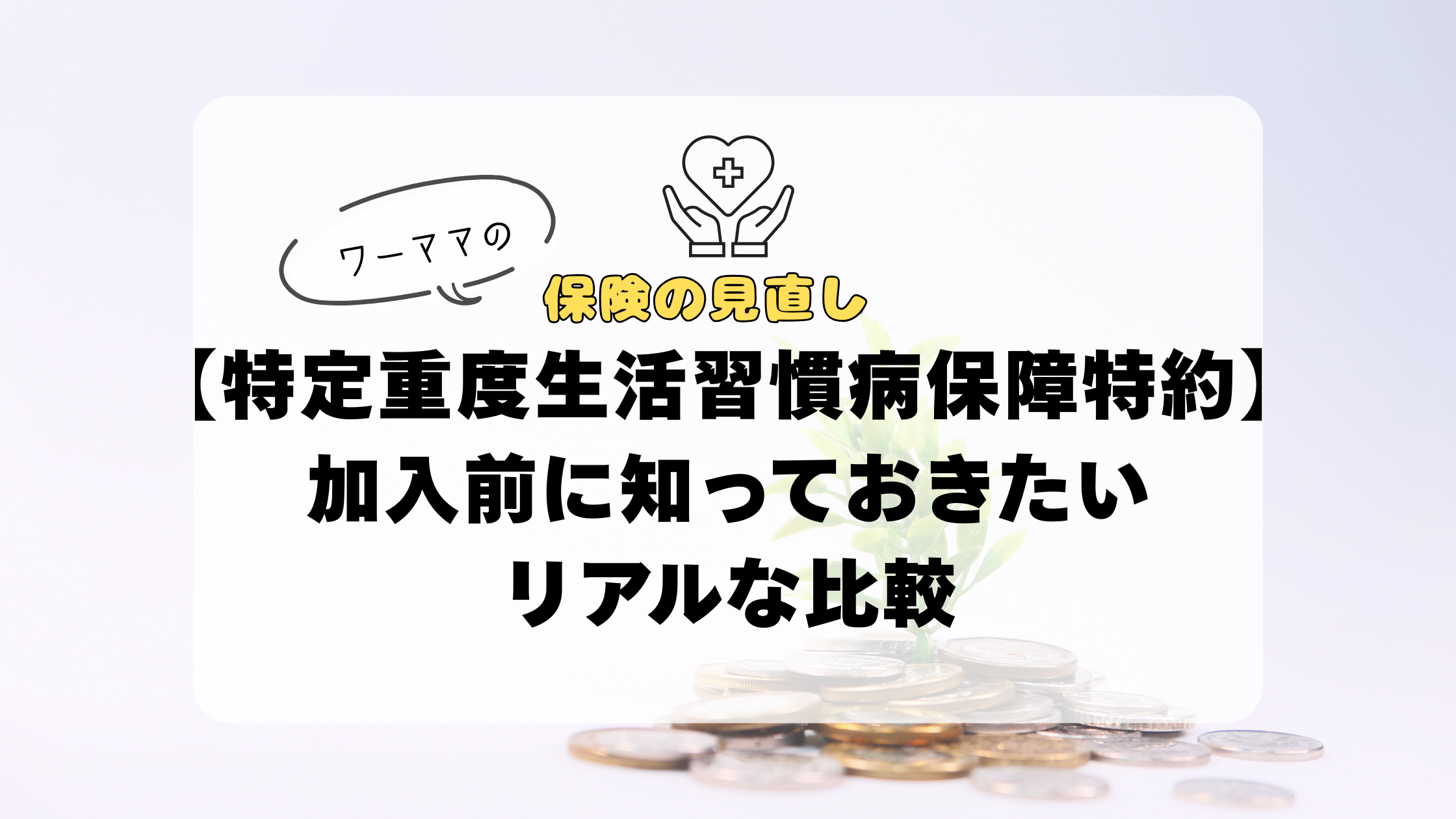
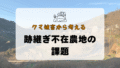
コメント