我が家では、今年11月から夫が育児休業を取得予定です。
「パパママ育休プラス」という制度を使うことで、子どもが1歳2か月になるまで夫が育休を取れる仕組みになっています。
この記事では、制度の概要から実際のスケジュール例、夫の育休に期待することまでをまとめてみました。
男性の育休取得率と平均期間
厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」によると、男性の育休取得率は17.1%(前年13.97%から増加)。ただし、そのうち1か月未満の取得が約40%を占めています。
つまり、「制度はあるけど、実際には短期で終わっているケースが多い」というのが現状。夫が数か月単位で育休を取るのは、まだまだ珍しい部類かもしれません。
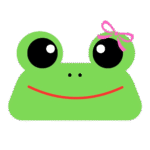
育休とは…。どうせ仕事の引き継ぎをするなら、しっかり休業期間を取ってみては?
パパ・ママ育休プラスとは?
「パパ・ママ育休プラス」とは、両親がともに育児休業を取得する場合に、子どもが1歳2か月まで育児休業を延長できる制度です。
通常、育休は「子が1歳になるまで」ですが、以下の条件を満たすと、2か月延長が可能になります。
- 両親ともに育児休業を取得すること
- 子の1歳2か月の誕生日の前日までにそれぞれの育休を開始すること
たとえばママが先に育休を取り、その後交代でパパが育休を引き継ぐような形もOK。家族のライフスタイルに合わせて、柔軟に期間を設定できるのが特徴です。
育休スケジュール(例:6月20日生まれの場合)
我が家の第2子の娘の誕生月は6月。
子どもが6月20日生まれだったと仮定して考えてみます。
スケジュールを具体的に当てはめると、以下のようなイメージになります。
▶保育園に入園できた場合
- ママ:産後休暇後〜翌年6月19日(子が1歳になる日)まで育休
- パパ:翌年11月から翌々年8月19日(子が1歳2か月)まで育休
→ 夫が1歳2か月まで育休を取れるので、
1歳児クラスの保育園入園に向けてしっかり準備期間を取れます。
▶保育園に入園できなかった場合
保育園の入園が叶わないときは、パパの育休終了後に、ママが再度育休を延長できる場合もあります。
ただし、再取得には「ママの職場が育児休業を認める」ことが必要です。
また、育児休業給付金の再支給には雇用保険上の条件※を再度満たす必要があるため、「交代制の再育休」はややハードルが高いのが現実です。
※再支給のために必要な「雇用保険上の条件」
厚生労働省が定めている主な条件は以下の通りです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 雇用保険に加入している | 休業前に雇用保険の被保険者であること(パートでも可) |
| ② 育児休業開始日前の2年間で、賃金支払いのある月が12か月以上ある | 1か月に11日以上働いた月が12か月以上必要(※復帰後に期間がリセットされる場合あり) |
| ③ 育休中に賃金が支払われていない(または休業前の80%未満) | つまり実際にお休みしていることが必要 |
| ④ 会社に育児休業の届出をしている | 勝手に休んでいるだけではNG。会社を通して申請することが必要 |
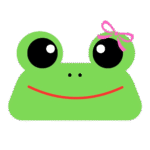
ママが先に仕事復帰したのち、子が保育園に入れないとき。今度はママがパパと交代で再度育休を取得するには、ママ側の会社に迷惑をかけてしまうかもしれません。復職前に事前情報として伝え、その前提で引き継ぎを行う必要がありますね。
妻が夫の育休に期待すること
SNSや調査を見ると、妻が夫の育休に期待するポイントは主に3つ。
- 家事・育児の戦力としてのサポート
→ 夜間対応、離乳食、洗濯、掃除などを「自分ごと」として担ってほしい。 - メンタル面での支え
→ ワンオペではない安心感。小さな「ありがとう」「今日どうだった?」の声がけが心強い。 - 家族時間を共有すること
→ 初めての発語、初めての一歩など、“子どもの成長を一緒に見守る時間”を大切にしてほしい。
私が夫の育休に期待すること
私自身が期待しているのは、「家事や子育てを自分ごととして捉える意識改革」です。
これまでなんとなく私の仕事だった料理や育児全般を、自分ごととして生活の一部にしてほしいと思っています。生活全般のものごとを考えるなかで、子供がいる前提が当たり前になってくれることに期待しています。
たとえば、休日のやることを考える際に、①掃除②買い物③読書 と考えるとします。
自分主体のスケジュール組みでは、朝食を食べたら①掃除をしよう。終わったら②買い物に行こう。買い物から帰ったら③読書をしよう とシンプルに考えるでしょう。
子供がいる前提のスケジュールだと、子が居たら遊んでほしいと言われるだろうから③読書の時間は早起きして朝にしよう。朝ごはんを食べたら①掃除をしよう。午前中に買い物を済ませたいけどお昼になりそうだな。子供の機嫌が悪くなるから午後に②買い物に行こう。買い物を午後にするなら午前中は公園に付き合おう。
という、子供の様子をイメージしたスケジュール組みを行います。これがぜひ出来るようになってほしいと思っています。
また、育休中は育児だけでなく、夫自身のキャリアや生き方を見つめ直す機会にもなればいいなと感じます。一緒に子どもと過ごす時間の中で、価値観をすり合わせたり、家族の「これから」を話し合える時間を持ちたいです。
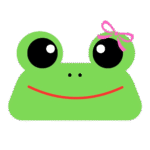
出世して!とは言いません。どんな未来を描くのか、そうするために何をするのか、夫婦でじっくり話したいなあ。
夫の育休中に意識したいこと
- 家事分担の「見える化」
- ストレスを溜めないための“1人時間”の確保
- 育児を「チームプレー」としてとらえる意識
夫が育休を取る=妻の負担ゼロ、ではありません。お互いのリズムを調整しながら、“共に育てる”時間を過ごすことが大切ですね。
まとめ
「パパママ育休プラス」は、家族にとって時間のゆとりを生む制度。
私たちにとっても、育児の主役が一時的にパパにバトンタッチされることで、新しい発見や絆の形が生まれることに期待します!

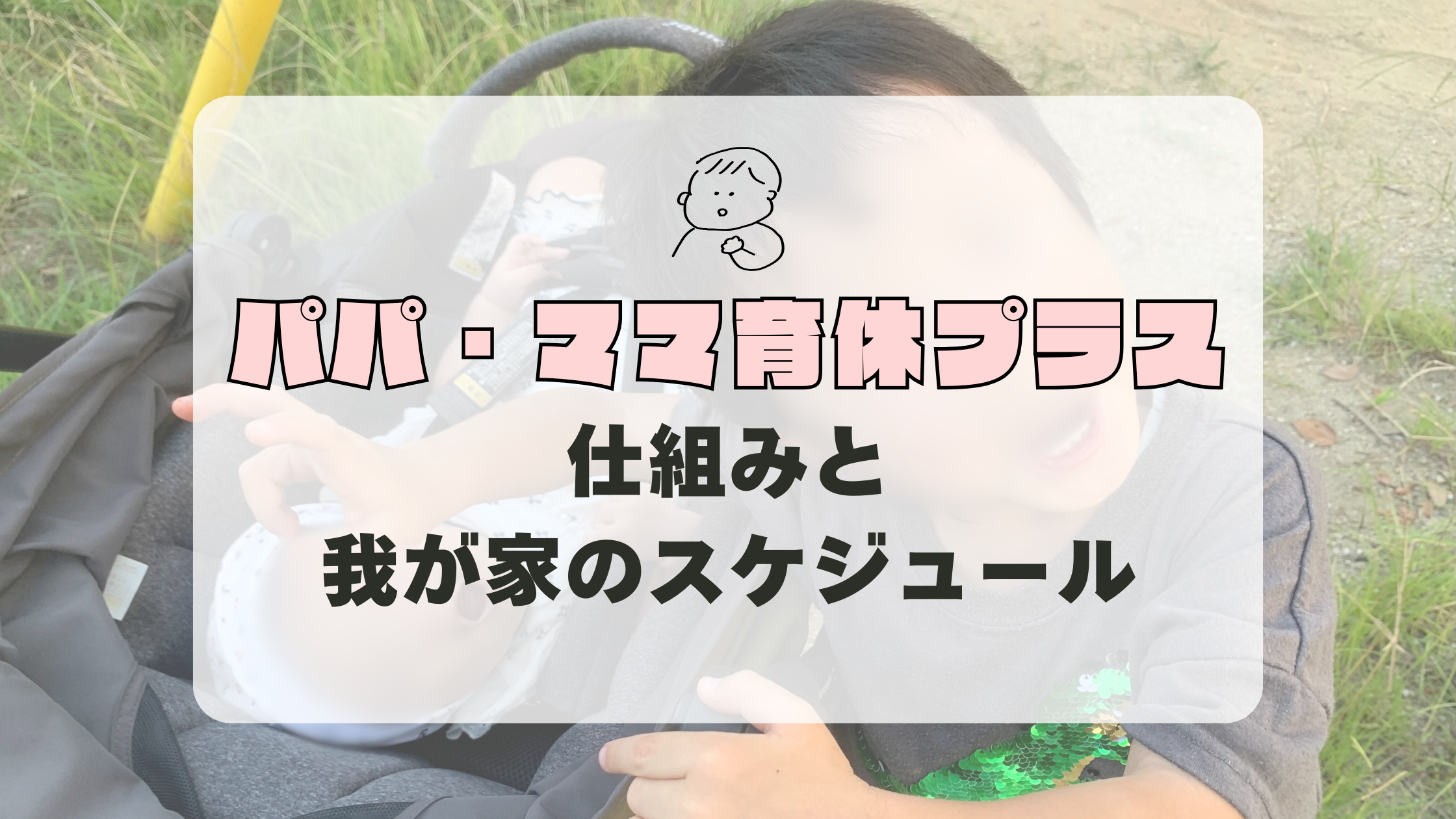
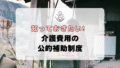

コメント